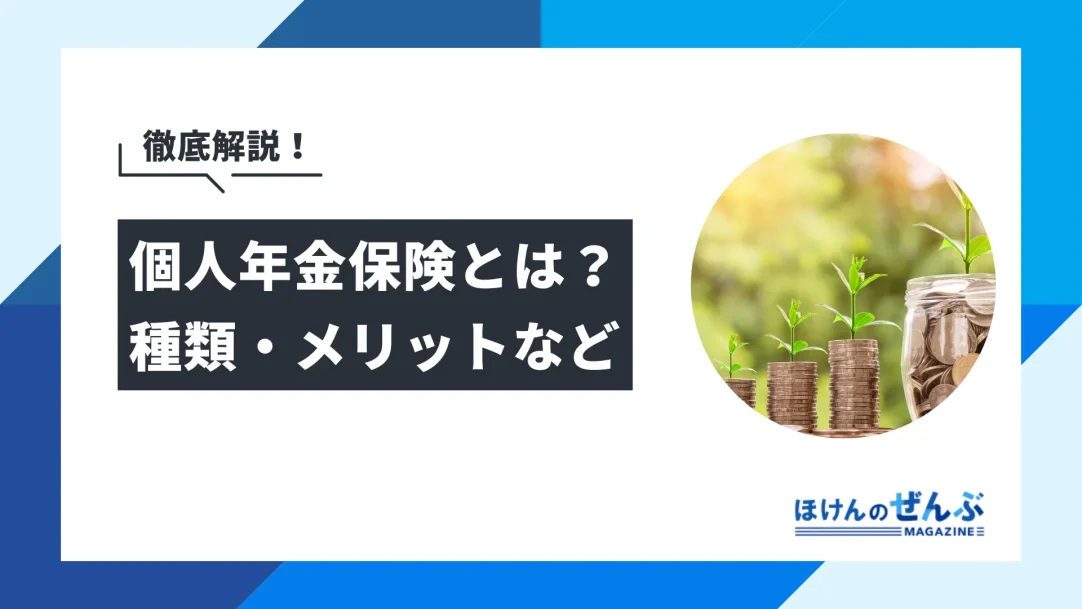銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

年齢を重ねるにつれて、老後資金の準備について気になっている方は多いのではないでしょうか。老後の資産形成の選択肢のひとつとしてよく挙げられるのが、『個人年金保険』です。
個人年金保険とは、保険会社と契約して将来の年金を自分で準備できる貯蓄性保険の一種です。
本記事では、個人年金保険の種類や加入のメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説していきます。

この記事の要点
- 個人年金保険とは、自分の老後資金を準備するために有力な方法のひとつです。
- 個人年金保険のメリットは、ローリスクで節税効果もあり、誰でも利用しやすく着実に老後資金を準備できる点です。
- しかし、インフレリスクに弱く、早期に途中解約すると損してしまうといったデメリットもあります。
- 個人年金保険への加入で後悔しないためには、専門家としっかり相談して検討しましょう。
- 無料保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、40社以上の保険商品から専門家があなたにぴったりの保険をご提案します。相談料は何回でも無料です。

この記事は5分程度で読めます。
目次
個人年金保険とは?
個人年金保険とは、自分自身の年金を準備するための保険です。保険会社と契約し、一定期間にわたり保険料を払い込むことで、保険会社はこれらの保険料を運用し、将来の年金原資を準備します。

編集部
公的年金との違い
日本で暮らす人は、公的な年金制度に必ず加入しているため、公的年金を受け取ることができます。しかし、多くの人が公的年金だけでは「老後の生活費を賄うことが難しい」と感じています。
このため、公的年金の不足を補うための自助努力が求められ、個人年金保険はその一環として利用されます。
このような自助努力で用意する年金を「私的年金」と呼び、個人年金保険もその一つです。
| 私的年金の種類 | 概要 |
|---|---|
| 個人年金保険 | 個人が契約する年金保険で、老後の生活資金を積み立てることを目的としています。 |
| 確定拠出型年金 (iDeCo) |
自分で掛金を拠出し、運用方法を選ぶことで、将来の年金を積み立てる制度です。 |
| 国民年金基金 | 自営業者やフリーランス向けの年金制度で、掛金を拠出することで年金を受け取れます。 |
| 小規模企業共済 | 小規模事業者向けの共済制度で、掛金を拠出して将来の資金を積み立てます。 |
個人年金保険は大きく3つの種類に分けられる
個人年金保険は、主に以下の3つに分類できます。
確定年金
万一、年金支給期間中に受取人が亡くなったとしても、決められた年金は必ず支給され、遺族が受け取ることができます。

編集部
本人にせよ遺族にせよ、決まった額の年金を受け取れることが確定しているので確定年金と呼ばれています。

なお、年金支給前に受取人が亡くなってしまった場合は、それまでに払い込んだ保険料総額が死亡給付金という形で返金されます。
この点は他の個人年金保険にも共通する仕組みです。
有期年金
生死にかかわらず決まった期間しか年金が支給されないので有期年金と呼ばれます。


編集部
死亡保障や家族に残すお金は別に用意するとして、年金はあくまで自分が生きている間に使うものという意図であれば、有期年金が適しているでしょう。
終身年金
受取人が亡くなった時点で支給は終わりますが、受け取り開始後5~10年の間に亡くなった場合は遺族に年金が支給される「保証期間」を設けている商品もあります。

しかし、それだけの年金原資を用意するために保険料は割高になっていますし、終身年金の受け取り総額が、保険料払込総額を上回る、つまり「元がとれる」ようになるまでには、相当の期間が必要です。

終身年金には、「夫婦年金」というタイプの商品もあります。
これは、夫婦を受け取りの対象として、いずれかが生きている間、年金が支給されるというものです。
また、すべてのタイプの個人年金保険で、年金形式で受け取るのではなく、一時金でまとめて受け取ることも可能です。
ただし、一括で受け取った場合、一時金の額は年金として受け取った場合の総額よりも少なくなります(受取期間中の運用ができないためです)。

編集部
個人年金保険に加入するデメリット
個人年金保険に加入することでデメリットとなり得る項目をご紹介していきます。
個人年金保険のデメリット
インフレに対応できない
個人年金保険の多くは、契約時点で受け取る年金額が決まっています。
このため、受け取り開始時期にインフレが進行すると、物価が上昇し、受け取れる年金の実質的な価値が下がる可能性があります。
このように、インフレリスクに弱いというデメリットがありますが、商品によっては「増加年金・増額年金」の仕組みがあり、運用成績に応じて年金額が増加する可能性があります。

編集部
インフレ対策を意識するなら、増加年金・増額年金のオプションがついている商品を選ぶと良いでしょう。
途中解約をすると損をする
個人年金保険を含めた貯蓄性保険に共通する特性として、早期の解約は損をします。
個人年金保険の場合、保険料払込期間中に解約した場合、受け取れる解約返戻金総額がそれまでに払い込んだ保険料総額を下回るケースがほとんどでしょう。

編集部
預貯金であればいつ引き出しても元本割れはしませんので、この点はデメリットに数えられますが、逆に、だからこそ一度始めたら解約したくないという心理がはたらくため、使い込みリスクを抑えてお金を貯められるという考え方もできます。
個人年金保険に加入するメリット
もちろん、個人年金保険にはメリットもあります。ここからは、メリットについて詳しくご紹介していきます。
個人年金保険のメリット
個人年金保険料控除の対象である
個人年金保険に加入していると、払い込んだ保険料額に応じて所得税・住民税を節税できる可能性があります。
所得控除とは
- 私たちは、年間に得た所得をもとに所得税・住民税を課税されています。
- しかし、やむをえず生じている費用などを、所得から差し引くことができる制度を所得控除といいます。
この控除の一つが、生命保険に加入して支払った保険料に応じて受けられる「生命保険料控除」です。
生命保険料控除には以下の3種類があります。
生命保険料控除の種類
- 生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
個人年金保険に加入して支払った保険料は、この「個人年金保険料控除」の対象となり、所得控除を受けることができます。

編集部
個人年金保険料控除の具体的な額
以下は、平成24年1月1日以降に加入した場合(新制度)の個人年金保険料控除額の一覧です。
| 年間の払込保険料等 | 所得控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |

所得税の税率が5%で課税されている人が、12万円の所得控除を受けた場合、課税所得総額が12万円低くなるのですから、所得税額が6,000円低くなったことになります。

編集部
なお、個人年金保険であれば必ず個人年金保険料控除を受けられるわけではなく、以下の条件を満たす商品・契約内容でなくてはなりません。
個人年金保険料控除対象の条件
- 年金の受取人が、契約者(保険料を払う人)本人か、その配偶者であること
- 受取人が被保険者であること
- 保険料を払う期間が10年以上であること
- 年金の受取開始時が60歳以降で、受取期間が10年以上であること
老後資金を着実に準備できる
個人年金保険に加入すると、契約した年金額が保証されるため、確実に老後資金を準備できる点が大きなメリットです。
保険料は口座引き落としやカード払いが一般的で、自動的に貯蓄が進む仕組みとなっています。

編集部
受け取れる年金総額を払い込んだ保険料総額で割れば、どのくらい増えたのかを返戻率として把握できます。現在、個人年金保険の返戻率は105~110%が主流です。
老後資金を準備することは先延ばしにしがちですが、個人年金保険なら着実に貯められるため、安心して老後に備えられるでしょう。
健康状態に不安があっても加入しやすい
個人年金保険は健康状態や病歴による告知や医師の診査が不要なケースが多く、健康リスクが高い方でも安心して加入できるというメリットがあります。
こういった特性から、病歴や現在の健康状態に自信がなくても、将来に向けた貯蓄を始めやすいという利点があります。
万が一、加入後に健康状態が悪化しても、契約内容に影響を与えることが少なく、安定した年金受取が可能です。

編集部
個人年金保険って必要?不要?
結論から言うと、個人年金保険は全ての人に「絶対おすすめ」というわけではありませんが、「リスクを避けつつ老後資金を着実に準備したい方」や「長生きリスクに備えたい方」にとっては、有効な選択肢です。
その理由を以下に説明します。
投資するリスクを避けたい人には向いている
個人年金保険は、投資リスクを負うことなく、預貯金よりも良い利率で着実に老後資金を準備したい方に向いています。
一方、積極的に資産を増やしたい場合は、元本保証がない代わりに高いリターンが期待できるi確定拠出型年金(iDeCoやつみたてNISAといった投資商品を検討すべきでしょう。

編集部
終身年金として長生きリスクに備えられる
老後資金の大きな課題の一つは、人生の期間が予測できないため、必要な資金総額を正確に把握しにくい点です。
公的年金は終身で受け取れますが、その他の制度や民間の商品で終身で受け取れるものは多くなく、自営業者だけが利用できる国民年金基金など、かなり限られています。
保険料は割高になる傾向があり「元をとる」ことが難しい可能性もありますが、一生涯の安心を得られる選択肢のひとつとしては、注目に値するでしょう。
誰でも加入しやすく、利用しやすい
個人年金保険は、他の保険商品と比較して告知項目が少ないため、比較的加入しやすいという特徴があります。
さまざまな私的年金制度があることはお伝えしましたが、国民年金基金は自営業者だけが、企業年金や財形年金貯蓄は導入している企業の従業員だけが使える制度であり、立場を問わずに使えるものは限定されます。
その点、個人年金保険は誰でも利用しやすい老後資金準備の方法としての価値があります。
個人年金保険の加入におすすめの無料相談所
ここまで個人年金保険について紹介してきましたが、「個人年金保険は種類が多くて自分にはどれが最適か分からない」と迷う人も多いはずです。
そこで、ここからは個人年金保険選びにおすすめの無料保険相談窓口をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
ほけんのぜんぶ

- 個人年金保険のメリット・デメリットを分かりやすく解説
- インフレリスクに対応した商品も紹介可能
- 取扱保険会社は41社※2
「ほけんのぜんぶ」は、生損保のあらゆる商品を提供している無料相談窓口。プロであるファイナンシャルプランナーが、利用者の「保険」「お金」に関するさまざまな悩みを解決に導きます。
また、在籍している多くのFPはプロ目線で相談者に寄り添った面談を心がけています。
取扱保険会社は41社※1で商品も豊富にあるので、インフレリスクに対応した商品紹介も可能です。

編集部
まとめ
今回は、個人年金保険の仕組みや種類など基本をわかりやすく解説しました。
個人年金保険とは、老後の資金を準備するための有力な手段の一つです。投資に比べてリスクを抑えながら資産を積み立てることができ、また保険料の控除による節税効果など、独自のメリットがあります。
しかし、個人年金保険はインフレリスクに弱く、早期に途中解約すると損してしまうといったデメリットもあります。
そのため、もし高利率で貯めることを重視するのであれば、iDeCoやつみたてNISAなども活用しながら老後資金に備えるのがおすすめです。

編集部
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。 ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。 また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

生命保険の業界歴10年。年間500世帯の相談実績。 社会保険・税金の効率化、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資と幅広い分野に精通。