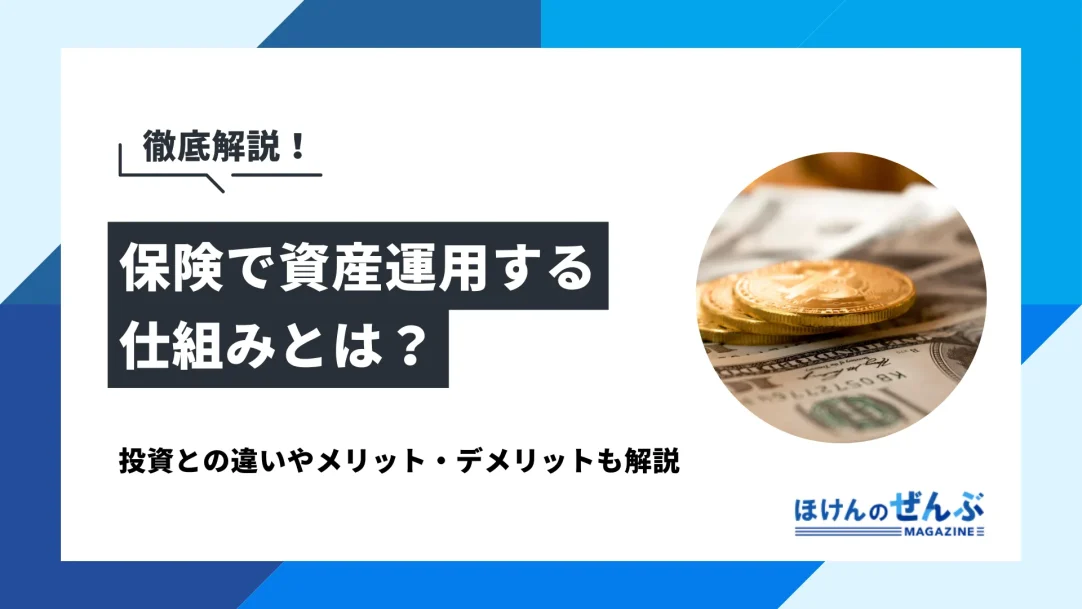銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

「保険=万が一のときの保障」というイメージを持っている人は多いでしょうが、一部の保険では保障に加えて資産運用をすることも可能です。
とはいえ、「保険で資産運用する仕組みがわからない」「投資とどのような違いがあるの?」といった疑問を持つ人もいるでしょう。
そこで本記事では、保険で資産運用する仕組みや投資との違い、メリット・デメリットについて詳しく解説しています。

編集部
- 保険で資産運用ができるのは「貯蓄型保険」で、保障と資産形成を同時に行えます。
- 保険での資産運用は投資(NISA・iDeCo)と比べて運用効率は劣る傾向にありますが、保障や税制優遇があるのが特長です。
- 金融知識がなくても始めやすく、元本確保型の保険もあるため初心者に向いています。
- ただし、短期解約や自由度の低さには注意が必要です。長期視点での運用が前提となります。
- 「保険での資産運用が自分に合っているのか分からない」という方は、ほけんのぜんぶの無料相談がおすすめです。経験豊富なプロが、納得できるまで丁寧にサポートしてくれます。

この記事は5分程度で読めます。
目次
保険で資産運用する仕組み
保険は大きく分けて「掛け捨て型」「貯蓄型」の2種類に大別され、資産運用ができるのは貯蓄型の保険を契約した場合です。
- 掛け捨て型:保障に特化しており、保障条件を満たさなければ支払った保険料は戻ってこない。
- 貯蓄型:保険料の一部を運用し、保障と資産運用を両立している。
貯蓄型保険は保険料の一部が保険会社によって運用される仕組みで、解約返戻金や満期保険金などにより後々お金を受け取れます。
もちろん、保険の本来の目的とも言える保障も兼ね備えているので、支払い要件に該当した場合での保険金受取も可能です。このように、保障と資産運用を1つの商品で両立している点が大きな特徴です。
保険と投資(NISA・iDeCo)の資産運用の違い
資産運用というと、NISAやiDeCoといった税制優遇制度のある投資を思い浮かべる人も多いでしょう。NISA・iDeCoによる資産運用は、貯蓄型保険での資産運用と大きく異なるので、違いをしっかり理解しておくことが大切です。
| 貯蓄型保険 | 投資(NISA・iDeCo) | |
|---|---|---|
| 運用の主体者 | 保険会社 | 口座保有者自身 |
| 金融知識の必要性 | なし | あり |
| 保障 | 死亡保障などあり | 原則なし |
| 運用効率 | 投資より劣る傾向 | 良い |
| 税制優遇制度 | 生命保険料控除 | 運用益非課税 掛金所得控除(iDeCoのみ) |
貯蓄型保険と投資による資産運用の大きな違いは、運用の主体者です。貯蓄型保険は保険会社が運用するのに対し、投資は口座保有者自身が運用商品や購入タイミングを選択します。
また、貯蓄型保険は保険会社に運用を任せる分、手数料は投資よりも割高傾向です。同じ運用成績の場合は、自身で運用して手数料を抑えられる投資の方が運用効率は良いでしょう。
一方で、投資の場合は万が一の事態に対する保障がないので、備えを別で確保しておく必要があります。
税制優遇制度は貯蓄型保険・投資(NISA・iDeCo)の両方にあり、どちらの制度が良いかは支払う保険料(投資元本)・運用成績によるため、一概には断定できません。

編集部
保険で資産運用する5つのメリット
保険で資産運用を行うメリットは主に以下の5つが挙げられます。
万が一に対する保障が備わっている
保険を使った資産運用の大きなメリットは、万が一に備えた保障が同時に得られる点です。例えば、死亡保障のある貯蓄型保険では資産形成の途中で契約者が亡くなっても、遺族などの受取人が死亡保険金を受け取ることができます。
通常の投資でも死亡時点での運用商品を遺族に渡せますが、運用成績によっては少ない金額しか残らないリスクもあります。

編集部
税制優遇制度を活用できる
保険で資産形成を行うと、以下2つの税制優遇制度を活用できる点もメリットです。
- 生命保険料控除(所得税・住民税の軽減)
- 死亡保険金の非課税枠(相続税の軽減)
生命保険料控除(所得税・住民税の軽減)
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料のうち一定額まではその年の課税所得から控除される制度のこと。これにより、所得税や住民税の負担を軽減させることができます。
生命保険料控除は、加入する生命保険の種類に応じて「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類に分けられ、各控除の上限は所得税4万円、住民税2.8万円です。
| 種類 | 該当する主な保険 | 控除上限 |
|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 終身保険・学資保険・養老保険 | 所得税:4万円
住民税:2.8万円 |
| 介護医療保険料控除 | 介護保険・医療保険・がん保険 | |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険 |
※2012年1月1日以降に締結された保険契約の場合。2011年以前に締結された保険契約は上限額が異なる。
3種類の生命保険料控除は併用※できるのも特徴です。例えば、終身保険・医療保険・個人年金保険に加入しているケースでは、3つ全ての控除を併用できており、高い節税効果を見込めます。
投資でも、NISAのように運用益が非課税になる優遇制度は存在していますが、NISAの場合は利益が出なければ優遇制度を活用できているとは言い難いです。

編集部
※:併用時は所得税で12万円・住民税で7万円が控除額の上限
参照:生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
死亡保険金の非課税枠(相続税の軽減)
相続財産が多額になりそうな人は、死亡保険金の非課税枠を活用して相続税を軽減させることができます。
相続税には基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)※1があり、基礎控除の範囲内であれば相続税はかかりません。しかし、これを超えた分に関しては相続税が発生します。
一方、保険を使わずに投資だけで資産運用していた場合は、死亡保険金の優遇制度は当然使えず、運用者が死亡しても基礎控除分しか控除を受けられません。
つまり、相続税の基礎控除を超える相続が想定される人は、保険を活用することで相続税の非課税枠を拡大して、相続税の負担を軽減することが可能です。

編集部
※1:国税庁「相続税の計算」参照
※2:国税庁「相続税がかからない財産」参照
資産運用に関する知識はあまり必要ない
保険を使った資産運用では保険会社が運用を代行してくれるため、契約者自身に金融知識がなくても取り組みやすいのがメリットです。
一方、投資の場合は自身で判断することが多いため、金融知識がない状態で始めるのはリスクがあります。
- 投資対象の選定
- 投資金額の設定
- 売買のタイミング
知識のない投資初心者が「なんとなく」判断してしまうのは危険であり、誰にでも取り組みやすいとは言い難いでしょう。
その点、貯蓄型保険での資産運用は専門的な判断が不要なため、初心者にとってハードルが低く堅実な資産形成の手段となり得ます。
元本確保型で安全な商品もある
貯蓄型保険には、保険を継続していれば元本が確保されるタイプの商品も存在します。契約時点で加入期間に応じた解約返戻金・満期保険金が決まっていることが多く、加入期間が一定年数を超えると元本以上の金額を受け取れる仕組みです。
投資の場合は元本割れリスクを完全には避けられないうえ、いつ・どのくらいの資産になっているかは推測ベースでしか判断できません。
資産運用をするうえで、「資産が減るリスク」を懸念する人や将来の資金計画を明確にさせたい人にとっては、元本が確保された保険商品は有力な選択肢になるでしょう。
借入できる商品もある
解約返戻金がある保険の場合「契約者貸付制度」を利用できるのも特徴の1つです。
自宅の修繕費や突発的な事故による医療費など、急に大きな出費が発生するケースは誰にでも起こり得るでしょう。イレギュラーの事態が起きたとき、十分な貯蓄がない家庭でも備えを維持しつつ資金を確保できる点は大きな安心材料です。

編集部
保険で資産運用する5つのデメリット
保険による資産運用はメリットだけでなく、以下のデメリットも存在します。
デメリットも踏まえたうえで、保険での資産運用を判断することが重要です。
運用先を自分で選べない
運用先を自ら選びたい人にとっては、保険による資産運用は自由度が低く、物足りなさを感じるかもしれません。保険会社に運用を任せることは、時間や手間がかからないといった利便性がある一方で、自分の判断で資産を増やしたいと考える人には不向きです。

編集部
一定のリスクを許容しつつ、より積極的な運用を望む場合は、投資など他の選択肢も視野に入れると良いでしょう。
自身で運用するよりコストが高い
保険を使った資産運用では、自身で運用するよりもコストは高くなる傾向です。
一方、NISAやiDeCoなど自ら商品を選んで運用する投資であれば、購入手数料や信託報酬などのコストが明確です。NISA口座でも購入できる人気の投資信託の中には、信託報酬※が年0.1%未満という低水準のものも存在します。
仮に運用成績が同じだった場合は、運用コストが低い方が多くの資金を手元に残せるので、コストをできるだけ抑えることが、資産を効率的に増やすうえで重要です。

編集部
長期で資産運用する場合、運用コストの差が将来の資産額にも大きな影響を及ぼすため、利便性やリスクだけでなくコストにも目を向けることが大切です。
※:投資信託を管理・運用してもらうための経費
途中で保険料を変更しにくい
保険は、契約時に決めた保険料を長期間にわたって継続的に支払う仕組みが基本です。そのため、途中で保険料の金額を増減しにくいデメリットがあります。
NISAやiDeCoといった投資であれば、以下のように、収入状況や家計の変化に合わせて積立額を柔軟に増減可能※。家計状況に合わせて、無理なく資産形成を継続できるのが特徴です。
- ボーナス支給月だけ積立額を増やす
- 急な出費により、一時的に積立額を減らす
- 家計状況の悪化により、積立を一旦停止
保険の場合は柔軟な対応が取れないため、一度契約した内容を変更するには、一旦解約して新たな契約を結び直す必要があります。多大な手間がかかるため、契約段階で長期的な支払い計画を事前に慎重に立てておくことが不可欠です。
※:iDeCoの積立額変更は年1回まで。(iDeCo公式サイト「加入者の方へ」)参照
短期解約すると元本割れの可能性が高くなる
貯蓄型保険の場合、契約から数年間は解約返戻金が少なく設定される商品がほとんどで、短期間で解約すると元本割れのリスクが高いです。
返戻率は商品ごとに異なるものの、保険加入期間に比例して上昇していくのが基本であり、加入期間が長いほど受け取れる解約返戻金も多くなります。
もし途中解約により元本割れとなった場合、当初の目的であった資産形成効果も限定的になりかねません。短期で使う可能性のある資金は別に管理しておき、保険は余剰資金を活用するのが現実的な選択と言えます。
保険料は掛け捨て型より割高
貯蓄型保険は保障に加えて資産形成機能も持つため、同じ保障内容で比べた場合は掛け捨て型の保険よりも保険料が高くなる傾向です。
保険料の一部を運用に回しているので、保険料が高くなるのは仕方ないことではありますが、保障を重視する人にとっては保険料が割高に感じるかもしれません。
保険での資産運用を望まない人や保障を手厚くしたい人は、掛け捨て型保険に加入する方が保険にかけるコストを抑えられます。
ただし、掛け捨て型では資産運用できないため、他の方法で資産形成の環境を整えていくことを考えましょう。
資産運用に向いている6種類の保険
資産運用に向いている保険の種類としては、以下の6種類が挙げられます。
終身保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
終身保険は、死亡保障が一生涯にわたって続く保険です。被保険者がいつ亡くなっても死亡保険金が遺族(受取人)に支払われるので、確実に保険金を残せる安心感があります。
終身保険は、契約時から保険料が変わらない点もメリットの1つです。年齢とともに保険料が上がる心配がないので、資金計画も立てやすくなります。
また、払込を早期に終えれば、その後は保険料負担なしで保障のみ継続させることも可能です。例えば、定年前に保険料を全て払い込めば、老後に保険料を支払う必要はありません。
一方で、短期間で解約すると返戻率が低く、元本割れするリスクが高い点には注意が必要です。加えて、保障が一生涯続くため、定期保険のような更新タイミングがないので、保険の見直しをしにくいこともデメリットになり得ます。

編集部
養老保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
養老保険は、一定の保険期間中に死亡した場合には死亡保険金が、満期まで生存した場合には満期保険金が支払われる保険です。死亡・生存のいずれでも同額の保険金が受け取れるため、保障と貯蓄を両立できる点が大きな魅力と言えます。
また、養老保険の満期保険金はすぐに受け取らず、保険会社に据え置くことも可能です。据え置き期間中も所定の利率で運用を継続してくれるので、金額が増えた状態で必要なときに受け取ることができます。
一方で、保障と貯蓄を同時に確保するため、保険料は終身保険よりも割高です。また、保険の満期後は保障がなくなり、満期保険金は払込保険料を下回るケースもあり得る点は注意してください。

編集部
学資保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
学資保険は、子どもの教育資金を準備するための保険です。子どもの進学時期に合わせて保険期間を設定し、満期時には満期保険金を受け取ることができます。また、満期前の節目(高校入学時など)に、お祝い金(一時金)を受け取れる商品もあります。
一方、途中解約すると元本割れするリスクが高く、長期間の継続が前提の保険と言えます。
さらに、教育資金が目的の商品であることから、契約できるのは子どもが小さい時期だけ。一定年齢(6〜7歳までが一般的)を超えると、加入できなくなるので注意しましょう。

編集部
※:保険料払込免除の特約は、すべての学資保険に付帯しているわけではありません。加入を検討する際は、必ず契約内容を確認しましょう。
個人年金保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
個人年金保険は、老後資金の準備を目的とした私的年金保険です。保険料を積み立てていき契約に指定した年齢に達すると、一定額の年金を受け取ることができます。
個人年金保険は、公的年金(国民年金・厚生年金)の不足分を補う手段として活用できるのがメリットです。有期年金・確定年金・終身年金など種類も複数あり、年金の受取期間などが異なるため、ライフプランに合わせて選択できます。
また、老後資金が目的の保険であるため、健康状態に不安がある人でも加入しやすいのも特徴です。終身保険のような死亡保障が目的の場合、健康状態によっては加入することができません。その点、個人年金保険であれば、他の貯蓄型保険に入れない人の資産運用手段にもなり得ます。
一方、契約から受取開始までは長期にわたることが多く、その間に途中解約すると元本割れするリスクは避けられません。さらに、契約時点で受取額が決まっている定額型の場合は、インフレ(物価の全体的な上昇)によって実質的な受取額が目減りする懸念もあります。

編集部
変額保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
変額保険は、運用成果によって解約返戻金や満期保険金が増減するタイプの保険です。定額型ではないためインフレの影響を受けにくく、運用成果次第で高いリターンを狙うことができます。
保障面では死亡保障が確保されているので、運用成績が悪い場合でも死亡保険金の保障金額は契約時に定めた金額を下回ることがない点もメリットです。
一方で、運用成績によっては満期まで保有しても元本割れする可能性があり、リスクを許容できない人には不向きです。また、保障が含まれる分、投資よりも利回りは良くない傾向です。純粋に投資目的なら、NISAのような制度を活用する方が効率が良いでしょう。

編集部
外貨建て保険
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
外貨建て保険は、円ではなく米ドルやユーロなどの外貨で保険料を支払い、その外貨にて運用される保険です。保険の種類は終身保険・養老保険・個人年金保険などがあり、保障内容自体は円建てとの違いはありません。
外貨建て保険は、円建てよりも高金利で運用されることが多く、長期間にわたって効率よく資産を増やす可能性があるのが特徴です。また、円以外の資産を保有することは、円相場が急落した際のリスク分散というメリットもあります。
一方、円高が進めば受取金額が目減りするリスクは避けられません。また、為替手数料は契約者負担になることが多く、円建てと比べるとコストが高くなる点はデメリットです。

編集部
保険での資産運用がおすすめな人・おすすめしにくい人の特徴
保険での資産運用はメリット・デメリットそれぞれがあるので、誰にでも適しているわけではありません。おすすめな人・おすすめしにくい人の特徴をそれぞれ紹介します。
おすすめな人の特徴
- 万が一の保障と資産運用を1つにまとめたい人
- 知識がなく専門家に任せたい人
- リスクをできるだけ抑えたい人
- 貯蓄が苦手な人
万が一の保障と資産運用を1つにまとめたい人は、貯蓄型保険がおすすめです。ライフプランに合わせて1つの商品で一元管理できるので、別々に管理する手間を省けるのが特徴です。
また、保険会社に運用を任せられるので、金融知識がない人でも手軽に運用できるのもメリット。安全性を重視した商品が多いため、基本的には資産を大きく減らす心配もありません。
貯蓄が苦手で将来の資金をなかなか貯められない人も、保険での資産運用は適しています。貯蓄型保険は短期解約すると元本割れしやすいですが、視点を変えれば半強制的に積立を継続できるとも捉えられます。

編集部
おすすめしにくい人の特徴
- 保険と投資を分けて考えたい人
- 高い利回りを求める人
- 投資にかかるコストを抑えたい人
「保障は保障、資産運用は投資で行いたい」と目的を明確に分けたい人には、保険での資産運用はおすすめしにくいです。保険はあくまで保障を目的とした金融商品のため、運用効率や自由度を重視するのであれば、投資商品を自ら選択する方が理にかなっています。
また、投資であれば高いリターンを期待できる商品を選ぶことも可能です。安定性を重視した貯蓄型保険での運用に物足りなさを感じる人は、保険よりも投資での資産運用が適していると考えられます。
さらに、貯蓄型保険は運用と保障を兼ね備えている分、手数料や諸経費が高めに設定されていることが一般的です。低コストで長期運用したい人にとっては、この点はマイナス要素になり得ます。

編集部
保険での資産運用に関するよくある質問
貯蓄型保険であれば、保険での資産運用が可能です。
死亡保障を重視するなら終身保険、子どもの教育資金を準備したいなら学資保険、老後の年金不足に備えるなら個人年金保険といったように、貯蓄型保険にも多様な種類があります。
どんな保障を確保したいかを考えて、加入する保険を判断することが重要です。
貯蓄型保険と投資の両方で資産運用することは問題ありません。両方の税制優遇制度を活用できるので、どちらか1つに絞るよりも大きな節税効果を見込めるでしょう。
ただし、投資だけに絞る方が運用効率は良くなる可能性があります。効率よく資産形成するなら保障・投資は分けて考えるのがおすすめです。
保険商品ごとに返礼率は異なるので、解約返戻金が元本を超える加入期間を一概に断定することはできません。
ただし、基本的には長期加入が前提になるので、10年・20年あるいはそれ以上のスパンでの加入が求められます。
また、返戻率100%を必ずしも超えるわけではないため、解約返戻金がいくらになるかは契約前にしっかり確認することが大切です。
将来の受取額が契約時点で決まっていると、物価高には対応しにくいです。受取時点で物価高が進行していれば、実質的な資産価値が目減りする可能性があります。
将来の物価高を懸念するなら、受取金額が運用成績に連動する変額保険での資産運用を検討すると良いでしょう。
投資で資産形成していても、保障のための保険は必要な人もいます。
現時点で、将来困らないほどの多額の資産があるなら、保険に加入する必要性は薄いです。しかし、これから資産を築いていく段階の人は、万が一のことを考えると保険に入っておく方が安心です。
保険に入っていなければ、急な病気による医療費の支払いなどで積み上げてきた資産がなくなるかもしれません。一方、保険に入っていれば保障があるため、投資の資産を残したまま急な出費にも対応できます。
保険料を抑えたい人は掛け捨て型の保険に加入して、万が一の保障だけは確保しておくのがおすすめです。
まとめ
本記事では、保険で資産運用をする仕組みやメリット・デメリット、資産運用に向いている保険の種類を中心に解説しました。
保険料の一部を運用する貯蓄型保険なら、保障と資産運用の両立が可能です。運用するのは保険会社なので、金融知識が薄い人や投資経験がない人でも取り組みやすい資産運用手段と言えます。
さらに、生命保険料控除を活用した税負担の軽減や、解約返戻金を担保にした契約者貸付制度を利用できるなど、保険での資産運用はメリットも多いです。
保険での資産運用は、保障と資産運用を1つの商品でまとめたい人やリスクを極力抑えたい人、貯蓄が苦手な人などにおすすめです。自身が該当していると感じた方々は、保険での資産運用を検討してはいかがでしょうか。