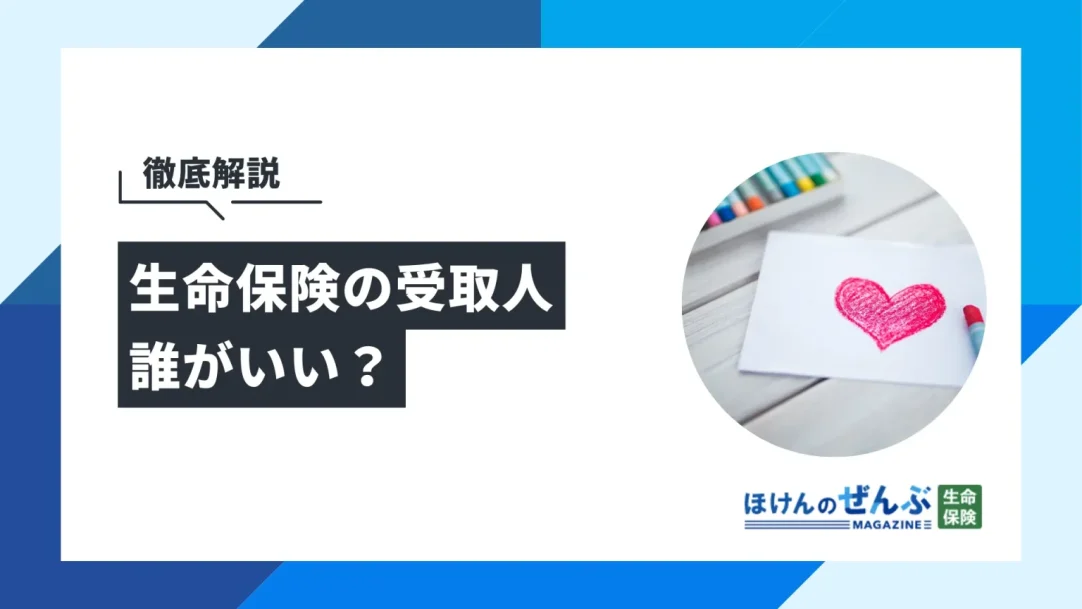銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

生命保険の「受取人」と言ったとき、それは「保険金受取人」を指します。つまり、保険金が支払われるとき、そのお金を受け取ると契約で決められている人のことです。
生命保険の受取人は保険を契約する人が指定すると思うのですが、誰でもいいのでしょうか?実は、受取人は誰でもいいわけではなく、また、受取人を誰にするかによって課税額が変わってくることもあるのです。
そこで今回は、保険金受取人について徹底解説。独身の方で配偶者や子供以外を受取人に設定したい場合についても解説します。
この記事の要点
この記事は5分程度で読めます。
※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
募集文書等の表示に係るガイドライン
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
広告等に関するガイドライン
目次
生命保険の受取人とは?
生命保険では、「保険契約者」「被保険者」「保険金受取人」という3つの役割があります。以下、それぞれの役割と関係について見ていきましょう。
生命保険における3つの立場
- 保険契約者:保険料を支払い、契約を結んだ人。一般的には加入者とも呼ばれます。
- 被保険者…保険の対象になっている人。契約者と同一の場合も、異なる場合もあります。
- 保険金受取人…保険金を受け取る人。契約内容により、被保険者本人が受取人になることもあります。
例①
Aさんは、自分が亡くなったら、配偶者のBさんに保険金が支払われる死亡保険に加入した。
保険料はAさんが負担している。
保険契約者:Aさん
被保険者:Aさん
保険金受取人:Bさん
例②
Aさんは、配偶者のBさんが亡くなったら、自身に保険金が支払われる死亡保険に加入した。
保険料はAさんが負担している。
- 保険契約者:Aさん
- 被保険者:Bさん
- 保険金受取人:Aさん
例③
Aさんは、配偶者のBさんが亡くなったら、ふたりの子であるCさんに保険金が支払われる死亡保険に加入した。
保険料はAさんが負担している。
- 保険契約者:Aさん
- 被保険者:Bさん
- 保険金受取人:Cさん

編集部
生命保険の受取人によってかかる税金は変わる
保険金受取人は、保険契約者や被保険者と同じ場合もあれば、異なる場合もあります。
死亡保険の場合、被保険者は保険金受取人と同じ人がなることはできませんが、保険契約者と被保険者は同じ場合も異なる場合も考えられるため、先ほど例に挙げた、
- Aさん
- Bさん(Aさんの配偶者)
- Cさん(AさんとBさんの子ども)
の家族で考えると、以下のようなパターンが一般的です。
| 保険契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | |
|---|---|---|---|
| パターン① | Aさん | Aさん | Bさん |
| パターン② | Aさん | Bさん | Aさん |
| パターン③ | Aさん | Bさん | Cさん |


編集部
パターン①相続税が課税されるケース
保険契約者が被保険者であり、その被保険者が亡くなることで支払われる保険金は、相続税法上は被保険者の相続財産とみなされます(みなし相続財産といいます)。
保険金の受取人が被保険者の相続人であれば相続として扱われ、それ以外の受取人であれば遺贈として扱われます。この場合、相続税が課税される可能性があることに注意が必要です。
ただし、相続税には基礎控除があり、また生命保険金には非課税枠(相続人一人当たり500万円×法定相続人数)があります。

編集部
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
パターン②所得税が課税されるケース
保険料を支払っていた契約者本人が保険金を受け取った場合、その保険金は契約者の一時所得として扱われます。このため、所得税が課税されることになります。
一時所得の計算方法
収入-収入を得るために支出した金額-特別控除(50万円)
「収入を得るために支出した金額」とは、支払った保険料の累計額です。
こちらの式で算出した一時所得を1/2した額が、その年のほかの所得と合算され、総合課税の対象となります。
パターン③贈与税が課税されるケース
保険契約者と被保険者、保険金受取人のすべてが違う人の場合、受取人が受け取った保険金は贈与税の課税対象になります。
保険金の出所は元をたどれば保険契約者のお金であり、この場合、そのお金を別の人が受け取っていて、かつそれが相続や遺贈ではないので、贈与であるとみなされるのです。

編集部
満期金などを自分で受け取った場合は?
もうひとつ、別のパターンとして、満期金や解約返戻金に関していえば、保険契約者・被保険者・保険金受取人のすべてが同一人であるケースも考えられます。

編集部
この場合も、パターン②と同じく、受け取った満期金などを一時所得と考え、所得税の課税対象になります。
生命保険の受取人になれる人は限られている


編集部
多くの保険会社では、原則として以下の人物でなければ受取人にはなれない、としています。
受取人になれる人
- 配偶者
- 2親等以内の血族である親族
血族とは、直接血のつながりのある親族をいいます。
注意点
配偶者の兄弟姉妹などは、2親等以内ですが、血族ではない(配偶者の親族は「姻族(いんぞく)」といます)ため、範囲に含まれません。

編集部
複数人でもOK。いつでも変更できる
なお、受取人になれる立場の人であれば、複数人を受取人とすることが可能です。


注意点
- ただし、受取人が複数名いる場合、受け取りの際の手続きを複数名で行わなくてはなりません。
- また、保険会社によっては、支払いは代表者に対してのみ行われます。
- そのため、複数人に保険金を渡したい場合は、契約自体を複数に分けて行ったほうが、スムーズかもしれません。
契約時に決めた受取人は、その後、手続きを行えば変更することができます。

編集部
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?」
生命保険の受取人に他人(第三者)はなれる?

まったくの他人(第三者)はモラルリスク(犯罪など保険が不適切に利用される可能性)の観点から保険金受取人になれないのが一般的でした。
しかし、近年、ライフスタイルが多様化し、上記にはあてはまらない「他人」だけれども、事実上は「家族」と呼んで差し支えない関係性を持つ人も少なくありません。

編集部
こうした人たちも、近年では、保険金受取人になることを認める保険会社が増えています。
事実婚・内縁関係の場合
実質的には結婚したような状態だけれども、法律上は婚姻をしていない状態を、「内縁関係」と呼びます。
内縁関係とは?
- 「事実婚」と内縁関係は同じ意味ですが、何か事情があって結婚しないのではなく、自分たちの意思であえて婚姻届を出していない状態を、内縁と区別して事実婚と呼ぶ人もいるようです。
- 事実婚・内縁関係でも、住民票には「夫(未届)」「妻(未届)」などという形で記載することが可能です。
事実婚・内縁関係のパートナーは、法律上の配偶者ではありませんが、保険会社は一定の条件で配偶者に相当するものとして、保険金受取人になることを認めるケースが多いです。
条件はおおむね、以下の3つです。
保険金受取人になるための条件
- 双方に配偶者がいないこと(別の人と法律上の婚姻をしていない)
- 同居していること
- 生計を同じにしていること
細かな点は保険会社ごとに規定があります。
たとえば同居の条件として一定期間以上の同居であることを定めていたり、必要な証明書類が指定されていたりするほか、訪問や面談をすることになっている場合もあります。
証明書類を求められる場合は、「戸籍謄本」と「住民票」が必要な場合が多いようです。
同性パートナーの場合
近年、性的マイノリティへの認知が広がる一方で、諸外国のように同性婚が認められていない日本では、自治体が独自に「パートナーシップ証明書」を発行するケースが増えています。

ポイント
事実婚・内縁関係と同様に、同居しているか、生計をともにしているかなど、パートナーとしての実態があるかを確認するプロセスを経て、受取人になることが可能です。
自治体が発行するパートナーシップ証明書は、保険会社の判断基準となる場合もありますが、すべての自治体で発行されるわけではなく、法律上の効力はないため、あくまで参考資料として扱われます。
そのため、保険金受取人を指定する際には、訪問や面談を通じて実際のパートナーシップの確認が行われるケースが多いようです。
参考:東京都総務局人権部「東京都パートナーシップ宣誓制度」
事実婚や同性パートナーが受取人になる場合の注意点


編集部
死亡保険金の非課税枠がない
事実婚・内縁関係や同性パートナーは、法定相続人になることができません。
通常、法定相続人である配偶者や親族が死亡保険金を受け取った場合、そのうち一定額は相続税の課税対象にならないという決まりがあります。
具体的には、法定相続人の数×500万円を限度とする非課税枠があり、相続人全体でこの額までは相続税が課税されません。
しかし、事実婚・内縁関係や同性パートナーは、たとえ保険金受取人であったとしても、相続人になれないため、この非課税限度額はありません。
※婚外子の父親が被相続人である場合、父親に認知されていれば法定相続分を有します。

編集部
生命保険料控除が使えない
生命保険に加入して、保険料を負担している人は、年間に払い込んだ保険料に応じて、生命保険料控除を受けることができ、所得税・住民税が抑えられる仕組みがあることは多くの方がご存じでしょう。
実は、生命保険料控除には「その保険金などの受取人がすべて、自分または自分の配偶者などの親族である場合」という条件があります(個人年金保険の場合は「年金の受取人が自分また自分の配偶者」)。
この条件に当てはまらない保険契約は、保険料を負担していたとしても、生命保険料控除は使えないのです。

編集部
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」」
生命保険の受取人になれる人がいない場合は?


編集部
その他の親族
配偶者も2親等以内の血族もいない場合、その他の親族を受取人として指定できる場合があります。
ただし、経済上・生活上の結びつきがあった(どちらかが経済的に支援していたとか、同居していたなど)ことなどを条件とするケースが多いようです。
特別縁故者
具体的には以下のような人物などを指します。
特別縁故者になりえる人
- 亡くなった人と生計をともにしていた人
- 亡くなった人の療養看護に努めた人
- 亡くなった人と特別な縁故があった人
事実婚・内縁関係や同性パートナーもこれにあたりますが、身よりのない人が入居していた福祉施設の運営法人が特別縁故者と認められるケースなどもあります。

編集部
受取人が被保険者より先に亡くなってしまった場合は?


編集部
被保険者からすると、保険金を残したい意図にそぐわないかもしれませんので、このような場合は、受取人を変更することを検討しましょう。
出典:公益財団法人 生命保険文化センター「死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?」
困ったらファイナンシャルプランナーに相談
生命保険は保険金の受け取り方によって、税金のかかり方が変わってきます。税金のことを理解しながら契約できるように、お金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
ここでは、おすすめの無料相談窓口を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ほけんのぜんぶ

- 生命保険に関する知識をFPが無料で提供
- 創業20年、累計31万件以上の申込実績で安心
- 40社以上の保険会社から最適な保険を見直し
ほけんのぜんぶでは、お金のプロであるファイナンシャルプランナーが生命保険や税金に関する相談に無料で対応してくれます。
相談は無料なので、まずは気軽に問い合わせをしてみましょう。

ほけんの縁結び

- FPが800名以上いるから価値観の合う相談相手に出会える
- なないろ生命のグループ会社運営だから安心!
- 経験豊富なベテランFPにじっくり相談できるから初めての相談におすすめ
ほけんの縁結びは、全国830名のファイナンシャルプランナーと提携しているお金の無料相談窓口です。
生命保険のことはもちろん、お金のプロであるファイナンシャルプランナーと相談することで、お金に関する悩みや心配事を解決することができるでしょう。
500商品以上ある保険の中から最適な保険を提案してくれるので、はじめてFP相談する方におすすめの相談窓口です。

まとめ
今回は生命保険の受取人についてお伝えしました。
生命保険の受取人は契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保障の対象になる人)、受取人の関係性によって、保険金を受け取ったときの税金の種類や課税対象額が変わります。
受取人に指定できるのは、配偶者や二親等内の血族が一般的です。しかし、内縁関係にある方や同性のパートナーを受取人に指定できる場合もあります。
結婚や離婚などで家族構成が変わった場合、受取人の変更を早急に行うことが重要です。これを怠ってしまうと、意図しない人が保険金を受け取る可能性があります。

編集部
また、受取人との関係によって、税金の種類が異なります。例えば、契約者と被保険者が同じで受取人が異なる場合、相続税が適用されます。適切な受取人を指定し、必要に応じて変更しましょう。
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。