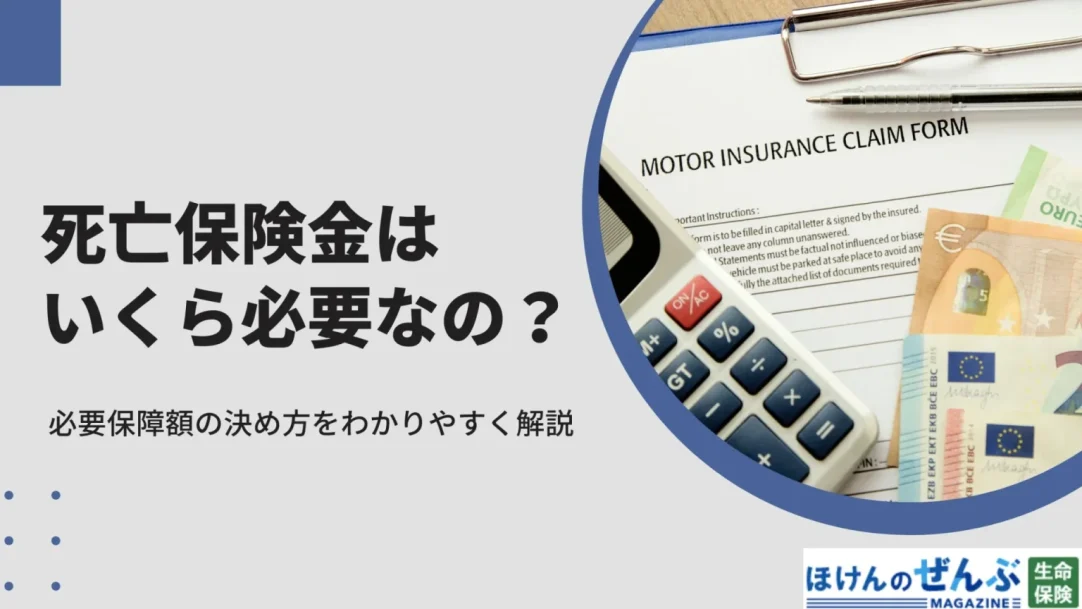銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

結論から言うと、生命保険の死亡保険金額は、家計状況や備えたい保障額によって異なります。とはいえ、死亡保険金額は家族構成・年齢・収入によって一定の傾向があります。
今回は生命保険文化センターの資料を参考に、年齢や収入、ライフステージ別に死亡保険金額の平均をご紹介します。

編集部

この記事の要点
- 死亡保険金の必要額は家庭の状況によって異なりますが、「生命保険に関する全国実態調査」によると、世帯主の平均的な死亡保険金額は1,936万円となっており、これを一つの目安として考えると良いでしょう。
- 死亡保険金を設定する際は、家族の生活費や住宅ローン、教育費など、必要な保障額を総合的に考慮することが大切です。具体的な金額を決めるためには、家計の状況や将来的な支出を見積もり判断する必要があります。
- もし不安な場合は、無料保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」で専門家からアドバイスを受けてみましょう。FP資格取得率100%※で、満足度の高い提案が期待できます。

※当社から訪問する入社1年以上のプランナーが対象
こちらの記事も読まれています
※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
募集文書等の表示に係るガイドライン
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
広告等に関するガイドライン
生命保険の死亡保険金はいくら必要?
生命保険の死亡保険金は一体いくら必要なのでしょうか?まずは他の人がいくらの死亡保険金を設定しているのかみていきましょう。
以下の表では、世帯主の死亡保険金額の割合をまとめています。
| 死亡保険金 | 割合 |
|---|---|
| 200万円未満 | 4.2% |
| 200万〜500万円未満 | 9.4% |
| 500万〜1,000万円未満 | 11.6% |
| 1,000万〜1,500万円未満 | 10.5% |
| 1,500万〜2,000万円未満 | 7.0% |
| 2,000万〜3,000万円未満 | 10.8% |
| 3,000万〜5,000万円未満 | 10.0% |
| 5,000万〜1億円未満 | 4.8% |
| 1億円以上 | 0.7% |
| 不明 | 31.1% |
1,000万円未満が全体の約2割、1,000万円から5,000万円未満は全体の約4割であることがわかります。

編集部
死亡保険金の平均額【年齢別】
| 年齢 | 平均死亡保険金額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 1,071万円 |
| 30〜34歳 | 2,001万円 |
| 35〜39歳 | 1,761万円 |
| 40〜44歳 | 1,676万円 |
| 45〜49歳 | 1,509万円 |
| 50〜54歳 | 1,624万円 |
| 55〜59歳 | 1,317万円 |
| 60〜64歳 | 1,093万円 |
| 65〜69歳 | 767万円 |
| 70〜74歳 | 598万円 |
| 75〜79歳 | 651万円 |
| 80〜84歳 | 480万円 |
| 85〜89歳 | 472万円 |
| 90歳以上 | 496万円 |
上の表からわかるように、死亡保険金の保障額は35〜39歳が1,761万円と最も多い金額となっています。
世帯主が35〜39歳の家庭には、子どもが高校・大学に通っているところが多く、死亡保険金の保障が厚くなっているのでしょう。

編集部
死亡保険金の平均額【世帯収入別】
| 世帯年収 | 平均死亡保険金額 |
|---|---|
| 200万円未満 | 607万円 |
| 200万〜300万円未満 | 761万円 |
| 300万〜400万円未満 | 985万円 |
| 400万〜500万円未満 | 1,246万円 |
| 500万〜600万円未満 | 1,446万円 |
| 600万〜700万円未満 | 1,513万円 |
| 700万〜1,000万円未満 | 1,932万円 |
| 1,000万円以上 | 2,495万円 |
次の表から死亡保険金額も、保険料と同じく収入が高いほど、多くなっているのがわかります。
収入が上がると死亡保険金額も上がる背景
- 収入が増えると、死亡保険金額も上がっていることから、自助努力で備える動きがあまりないことがわかります。
- その理由として、収入が上がるにつれて、生活水準が上がって、世帯主が亡くなった後に生活を維持するための死亡保険金額も高くなっていると考えられます。
死亡保険金の平均額【ライフステージ別】
世帯の状況によって、死亡保険金の設定額に差が見られます。特に子どもがいる家庭では、死亡保険金額が高く設定されている傾向です。
| 世帯状況 | 割合 |
|---|---|
| 夫婦のみ(40歳未満) | 962万円 |
| 夫婦のみ(40〜59歳) | 1,350万円 |
| 末子乳児 | 1,742万円 |
| 末子保育園児・幼稚園児 | 1,784万円 |
| 末子小・中学生 | 1,668万円 |
| 末子高校・短大・大学生 | 1,613万円 |
| 末子就学終了 | 1,009万円 |
| 高齢夫婦有職(60歳以上) | 805万円 |
| 高齢夫婦無職(60歳以上) | 551万円 |
出典:生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」P231
末子が乳児の家庭では死亡保険金額は1,742万円と非常に高く、末子が保育園児・幼稚園児の場合はさらに増えて1,784万円に達しています。
これは子どもの成長に伴い、生活費や教育費の負担が大きくなるため、家計の保障をしっかりと確保したいというニーズが反映されていると考えられるでしょう。
子どもが小・中学生や高校生になると、死亡保険金額は少しずつ減少し、末子が就学終了した段階で1,009万円にまで減少します。

編集部
共働きの妻の死亡保険金はいくら必要?
かつては女性が専業主婦になることが一般的でしたが、現在はフルタイムで働く女性も増え、夫と同様に生命保険の必要性が高まっています。
共働き家庭の場合、必要な死亡保険金額は夫婦の年齢、子どもの有無、住宅ローンの有無などによって異なります。ここでは、夫婦と子ども2人の家庭を例に考えてみましょう。
モデルケース
- 家族構成:夫(32歳)、妻(30)、子ども2人(4歳、2歳)
- 月収(手取り額):夫25万円、妻16万円
- 生命保険:夫:死亡保障3,000万円の生命保険に加入、妻:医療保険のみ
- 住宅ローン:借入金額2,500万円(夫が団体信用生命保険に加入)
夫が死亡した場合、住宅ローンは団体信用生命保険から支払われますので、生命保険で補う必要はありません。残りの備えは子どもにかかる費用です。
一般的に、子ども1人あたり2,000~3,000万円の備えが必要とされています。夫がすでに3,000万円の保障に加入していることを踏まえ、妻には2,000万円程度の死亡保障が望ましいでしょう。
共働きの妻の死亡保障の考え方
共働きの妻が必要な死亡保障は、夫の保障額を差し引いた額を目安に考えるのが良いでしょう。
遺族年金も受け取れる可能性はありますが、必ずしも十分な金額が受け取れるとは限らないため、自主的に備えておくことが大切です。
死亡保障をつけられるおすすめの生命保険
- 終身保険:一生涯の保障が得られるが、保険料が高い
- 定期保険:掛け捨て型で、安い保険料で大きな保障を得られる
- 収入保障保険:被保険者が死亡後、毎月年金のように保険金が支払われ、保障額が徐々に減るため保険料を抑えられる
生命保険の死亡保険金額の決め方
死亡保険金額を決める際、何を基準にすべきか迷う方も多いでしょう。統計上の平均値は参考になりますが、あくまで統計上の平均値にすぎません。
以下では実際に自分に合った保険金額を計算する方法を解説します。
1.必要保障金額を計算する
まず最初に、必要な保障金額を算出しましょう。死亡保険金額は、必要保障金額に基づいて決まり、保険料は選んだ死亡保険金額に応じて決まります。

編集部
必要保障金額は、簡単に言うと「収入を得ている人(世帯主)の死亡後にかかる支出に対する収入の不足分」を補う金額です。これには、以下の収入と支出を考慮します。
| 世帯主が亡くなった後の収入 | 世帯主が亡くなった後の支出 |
|---|---|
|
|
つまり、「世帯主が亡くなった後の収入−世帯主が亡くなった後の支出=必要保障額」となり、備えるべきおおよその死亡保険金額がわかります。
例えば、世帯主が亡くなった後、家族の収入が年間300万円、支出が年間250万円の場合、必要保障金額は「300万円 − 250万円 = 50万円」となります。
2. 保険料の検討
必要保障金額を計算したら、次にその金額に見合った保険料を支払えるかどうかを確認しましょう。家計状況を考慮して、無理なく支払える範囲で保険を選ぶことが大切です。
死亡保険金額が高すぎると保険料が負担になりやすいため、生活費やその他の支出を考慮しながらバランスを取ることが重要です。
3.専門家に相談する
生命保険の死亡保険金額を決める際、計算方法や選び方に迷うこともあるでしょう。その場合は、一人で悩まず専門家に相談するのがおすすめです。
無料の保険相談窓口を活用すれば、ライフプランや家計状況に応じた適切なアドバイスを受けられます。
専門家が将来のリスクや家族の生活保障に必要な金額を一緒に検討してくれるため、より安心して最適な選択ができるはずです。

編集部
死亡保険金の注意点
死亡保険金には、いくつかの注意点があります。
加入できる年齢に制限がある
多くの場合、生命保険には加入年齢に制限があります。若い頃に加入することで、保険料が低く抑えられる場合が多いため、できるだけ早く加入を検討するのが賢明です。
特に高齢になると保険料が高くなるうえ、加入条件が厳しくなることもあるので注意しましょう。
ライフステージごとの見直しが必要
人生のステージごとに必要な保障内容は変化します。結婚や子供の誕生、住宅ローンの借り入れなどの変化に応じて、死亡保険金や保障内容の見直しが必要です。
定期的な見直しで、過不足なく生活に合った保障を確保できます。例えば、子どもが成長したり、住宅ローンを完済したりした場合には保険金額を調整しましょう。
保険金額を高く設定しすぎない
死亡保険金額は、過剰に設定すると保険料が高くなりすぎてしまう可能性があります。必要な保障額を計算し、過不足ない金額に設定することが大切です。
過剰な保険金額を設定しても、実際に使いきれなかったり、家計に負担をかけることになります。家族の生活費や教育資金を考慮し、保障内容と保険料のバランスを取りましょう。

編集部
請求には期限が定められている
死亡保険金の請求には、契約内容や保険会社によって期限が設けられている場合があります。
期限を過ぎると保険金を受け取れなくなるリスクがあるため、万が一の際には早急に手続きを行いましょう。
必要な書類や手続きもあるため、あらかじめ家族や親族と共に準備しておくことが重要です。
税金が課せられる場合がある
死亡保険金には、相続税や所得税が課せられる場合があります。特に高額な保険金を受け取る場合や、複数の保険金を受け取る場合には注意が必要です。
税額の算出方法や具体的な手続きについては、専門家に相談し、適切に対応しましょう。税制が変更される可能性もあるため、定期的に確認しておくことをおすすめします。
出典:国税庁「No.1750 死亡保険金を受け取ったとき」
生命保険の死亡保険金に関してよくある質問
例えば、夫・妻・子ども2人の世帯で、生命保険の契約者かつ被保険者の夫が亡くなった場合、この場合、法定相続人は妻と子ども2人です。したがって、法定相続人3人×500万円=1,500万円の死亡保険金を非課税で受け取れます。
出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
まとめ
生命保険の死亡保険金額の平均は全体で1,936万円です。保険金額は、年齢や収入、家族構成、ライフステージによって一定の傾向があるため、自分の状況に最も近いところを参考にしてみてください。
まずは自分や自分の家族の必要保障額を「世帯主が亡くなった後の収入−世帯主が亡くなった後の支出」の式で計算し、保険金額と保険料を決めていくのがおすすめです。

編集部
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。