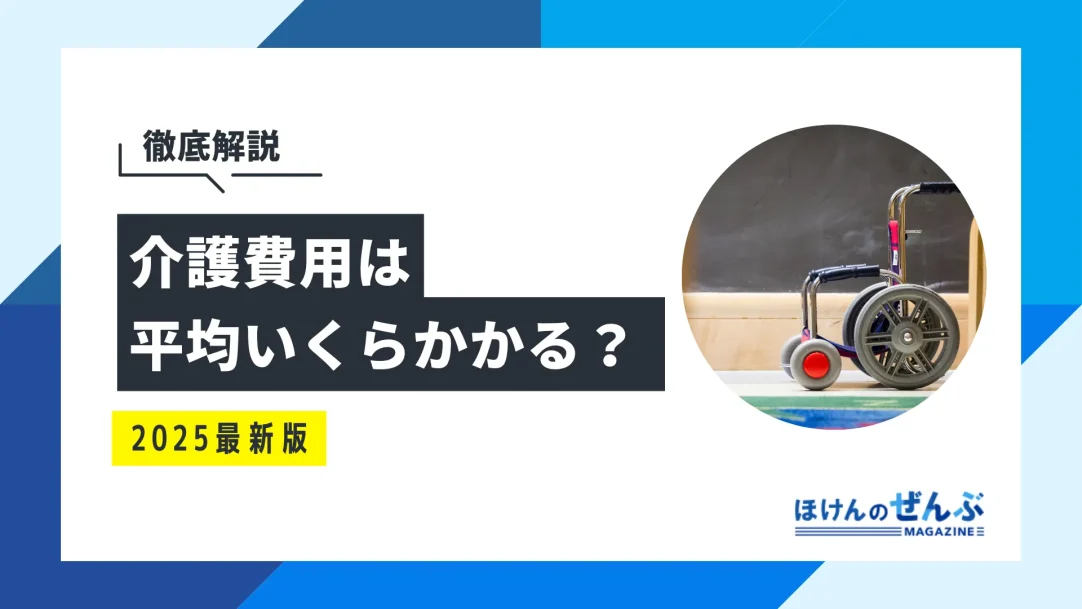銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

人生100年時代を迎え、老後の生活資金に対する関心が高まっていますが、もう1つ気になるのが親や自分の介護費用のことです。
「介護費用は平均いくらかかる?」「もしも介護費用が払えなかったらどうすればいい?」と不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、介護費用の相場(平均額)について詳しく解説します。

この記事の要点
- 介護の初期費用は平均47万円、毎月の費用は約9.0万円で、総額540万円ほどかかるとされています※。
- 公的制度を活用すれば費用負担を抑えられるが、収入減などのリスクには対応しきれない可能性も。
- より手厚く備えたい場合は、民間の介護保険を検討したり、専門家に相談したりすることをおすすめします。
- 無料保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」では、FP資格を保有した相談員が40社以上の保険商品からあなたに最適な保険をご提案!相談料は何度でも無料です。

※出典:生命保険文化センター「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査」
この記事は5分程度で読めます。
※本コンテンツで紹介している保険会社及び保険代理店は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品・サービスの一部または全部に広告が含まれています。しかし、コンテンツの内容や評価に一切影響する事はありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
募集文書等の表示に係るガイドライン
第三分野商品(疾病または介護を支払事由とする商品)に関するガイドライン
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
広告等に関するガイドライン
介護費用は平均いくらかかる?
「介護にかかる費用って、結局いくらくらいなの?」そう疑問に思う方は多いでしょう。
生命保険文化センターの最新調査(令和6年度 生命保険に関する全国実態調査)から、介護費用の平均額を見ていきましょう。
介護の初期費用(一時的な費用)
生命保険文化センターの調査によると、住宅の改造や介護用ベッドの購入など、介護を始める際にかかる初期費用は平均47万円です。
初期費用(一時的な費用)の分布
| 金額 | 割合 |
| 掛かった費用はない | 17.5% |
| 15万円未満 | 24.0% |
| 15〜25万円未満 | 10.1% |
| 25〜50万円未満 | 6.2% |
| 50〜100万円未満 | 7.2% |
| 100~150万円未満 | 6.4% |
| 150~200万円未満 | 1.8% |
| 200万円以上 | 4.7% |
| 不明 | 22.0% |
実際に介護を経験した人のデータでは、初期費用が「かからなかった」という人も17.5%いますが、一方で200万円以上かかったという人も4.7%います。
全体の半数以上は初期費用が25万円未満に収まっているものの、高額になる可能性もゼロではありません。
【要介護度別】初期費用
要介護度によって初期費用に差が見られますが、特定の要介護度が高いからといって、必ずしも初期費用も高くなるという明確な傾向は読み取れません。
| 要介護度 | 初期費用 |
| 要支援1 | 44万円 |
| 要支援2 | 44万円 |
| 要介護1 | 30万円 |
| 要介護2 | 54万円 |
| 要介護3 | 42万円 |
| 要介護4 | 52万円 |
| 要介護5 | 47万円 |
| 公的介護保険の利用経験なし | 68万円 |
| 公的介護保険の利用経験あり | 46万円 |
参考:生命保険文化センター「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査(P179)」(以下、同様)
毎月の介護費用
介護にかかる毎月の費用は平均9.0万円です。
これは、世帯主または配偶者が要介護状態になった場合に「必要と考える月々の費用(公的介護保険の範囲外含む)」(平均15.7万円)よりは少ないものの、家計にとっては継続的な大きな負担となりえます。
毎月の介護費用の分布
毎月の介護費用は、人によってかなり幅があるのが特徴です。
全体の約3分の1は5万円未満で済んでいますが、一方で10万円以上かかっている人も約30%いるため、自分のケースがどこに当てはまるかは予測しにくいのが現状です。
| 金額 | 割合 |
| 1万円未満 | 5.9% |
| 1万〜2万5千円未満 | 15.1% |
| 2万5千〜5万円未満 | 13.3% |
| 5万〜7万5千円未満 | 9.9% |
| 7万5千〜10万円未満 | 4.4% |
| 10万〜12万5千円未満 | 10.4% |
| 12万5千〜15万円未満 | 5.5% |
| 15万円以上 | 19.3% |
| 不明 | 16.1% |
【要介護度別】毎月の介護費用
毎月の介護費用は、要介護度が重くなるにつれて明らかに高くなる傾向があります。
特に要介護3以上になると、平均で月10万円前後と、経済的な負担がかなり大きくなることがわかります。
| 要介護度 | 毎月の介護費用 |
| 要支援1 | 5.8万円 |
| 要支援2 | 7.0万円 |
| 要介護1 | 5.4万円 |
| 要介護2 | 7.5万円 |
| 要介護3 | 8.5万円 |
| 要介護4 | 12.4万円 |
| 要介護5 | 11.3万円 |
| 公的介護保険の利用経験なし | 4.0万円 |
| 公的介護保険の利用経験あり | 9.1万円 |
介護期間
生命保険文化センターの調査によると、介護期間は平均4年7か月(55か月)です。
たとえ毎月の費用がそれほど大きくなくても、介護が長期間にわたれば、その分経済的な負担は増大します。
介護期間の分布
注目すべきは、介護期間が4年以上10年未満という人が最も多く(27.9%)、さらに10年以上介護が続いたケースも14.8%ある点です。
介護は短期で終わるとは限らず、長期化するリスクも考慮する必要があります。
| 期間 | 割合 |
| 6か月未満 | 6.1% |
| 6か月以上1年未満 | 6.9% |
| 1年以上2年未満 | 15.0% |
| 2年以上3年未満 | 16.5% |
| 3年以上4年未満 | 11.6% |
| 4年以上10年未満 | 27.9% |
| 10年以上 | 14.8% |
| 不明 | 1.3% |
これらの平均値を使って、介護費用の総額を試算すると以下のようになります。
- 毎月の介護費用(9.0万円)× 介護期間(55か月)+ 初期費用(47万円)= 542万円(介護費用の総額)
あくまで平均値に基づいた試算ですが、介護には約540万円もの費用がかかる可能性があると考えると、事前の備えの重要性がよくわかるでしょう。
在宅介護でかかる費用は?
次に、在宅介護にかかる費用について見ていきましょう
在宅介護にかかる費用項目
在宅介護にかかる主な費用は次の通りです。
在宅介護にかかる主な費用項目
- 介護用品:車椅子や介護用ベッドの購入費やレンタル費
- 訪問介護:介護福祉士などによる入浴・排せつ・食事の介助、買い物、食事作り など
- 訪問入浴介護:介護福祉士などによる入浴サービス
- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士によるリハビリ
- 通所介護(デイサービス):デイサービス施設での介護サービス
- 通所リハビリ(デイケア):デイケア施設での理学療法士や作業療法士によるリハビリ
- 短期入所生活介護(ショートステイ):介護施設での、宿泊を伴う食事・入浴・排せつなどの全般的な介護サービス
- 短期入所療養介護:介護老人保健施設や療養病床のある病院での、宿泊を伴う治療や医療を主とした介護サービス など
当然のことですが、要介護状態に関係なく食事や娯楽などの日常生活費用も必要です。
在宅介護の毎月の介護費用は平均5.2万円
前述の生命保険文化センターの調査によると、在宅介護の場合、毎月の介護費用は平均5.2万円です。費用は以下のような内訳になります。
| 金額 | 在宅介護 |
| 1万円未満 | 8.6% |
| 1万円〜2万5千円未満 | 22.8% |
| 2万5千円〜5万円未満 | 18.4% |
| 5万円〜7万5千円未満 | 13.0% |
| 7万5千円〜10万円未満 | 4.0% |
| 10万円〜12万5千円未満 | 6.3% |
| 12万5千円〜15万円未満 | 1.2% |
| 15万円以上 | 6.9% |
| 不明 | 18.7% |
在宅介護の場合、半数以上が毎月5万円未満の費用で済んでいますが、高額になるケースも一定程度存在します。
施設に入所する場合にかかる介護費用は?
生命保険文化センターの調査によると、介護施設を利用した場合の平均的な介護費用は月13.8万円です。
しかし、これはあくまでも目安で、利用する施設によって費用は大きく異なります。
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム(特養)は、社会福祉法人や地方自治体が運営する介護施設です。主な特徴は次の通りです。
特別養護老人ホームの特徴
- 介護保険が適用されるため、料金が比較的安い
- 対象者は原則65歳以上で要介護度3~5であること
- 入居一時金はなく、負担は月々の利用料のみ
- 入居希望者が多く、なかなか入所できない
また、特別養護老人ホームには次の3種類があります。
- 広域型特別養護老人ホーム:定員が30名以上、居住地も関係なく入所できる
- 地域密着型特別養護老人ホーム:定員が29名以下、地域に根差した小規模な老人ホーム
- 地域サポート型特別養護老人ホーム:対象は在宅介護を受けている高齢者、24時間年中無休の見守り体制で都道府県が認定した事業所がサービスを提供
特別養護老人ホームの費用
特別養護老人ホームの費用は、主に介護サービス費・居住費・食費・日常生活費の4つです。
特別養護老人ホームの費用では、所得に応じて「居住費(賃料)」と「食費」の負担限度額が設けられています。
また、利用する部屋のタイプ(個室や大部屋など)によって「居住費(賃料)」の負担限度額は異なります。
部屋のタイプ別の介護費用(介護サービス費+居住費+食費)は次の通りです。介護サービス費は要介護度によって異なります。
| 部屋のタイプ | 介護費用(介護サービス費+居住費+食費) |
| 従来型個室 | 9.7万円~10.1万円 |
| 多床室 | 8.8万円~9.2万円 |
| ユニット型個室 | 12.5万円~12.9万円 |
| ユニット型 個室的多床室 |
11.5万円~11.9万円 |
※ユニットは10人以下の小グループのこと。ロビーやダイニング、キッチン、浴室、トイレをユニット単位で共有して共同生活。
参考:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
有料老人ホーム
有料老人ホームは、民間が運営する高齢者施設で種類は様々です。健康で介護が不要な人が利用する有料老人ホームもあります。
有料老人ホームの種類
- 介護付き有料老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
- グループホーム
- ケアハウス など
ここでは、介護付き有料老人ホームについて紹介します。
介護付き有料老人ホームとは、都道府県から「特定施設入所者生活介護」の指定を受けた介護施設のことで、主な特徴は次の通りです。
介護付き有料老人ホームの特徴
- 対象者は「要介護者」
- 施設によって費用やサービスの内容が異なる
- 特別養護老人ホームと比較して費用が高額
有料老人ホームの費用
「みんなの介護」のサイトに掲載されている介護付き有料老人ホームの平均的な費用は次の通りです。
- 入居一時金:平均30万円
- 毎月の介護費用:平均20.3万円
引用:みんなの介護「介護付き有料老人ホームとは?サービス内容と知っておきたい入居条件」
平均値を紹介しましたが、介護付き有料老人ホームの費用は地域やサービス内容によって大きく異なります。

編集部
介護費用が払えない場合どうする?
要介護認定を受けた人は各種介護サービスを受けることができますが、介護サービス費用の1割(所得によっては2割または3割)は自己負担です。
この自己負担分が高額となり介護費用を払えない場合、費用を一定額に抑える仕組みが「高額介護サービス費」と「高額介護合算療養費」です。
1か月の介護費用が高額になった場合は「高額介護サービス費」
1か月の介護保険サービスの自己負担額が所定の限度額を超えると、超過分は払い戻しされます。

編集部
所定の限度額は2021年8月に改正され、所得区分に応じて次の通りとなりました。
高額介護サービス費の限度額
表は横にスライドできます
| 所得区分 | 限度額(1か月) | |
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円) | 14万100円(世帯) | |
| 課税所得380万円以上課税所得690万円未満 (年収約770万円) |
9万3,000円(世帯) | |
| 市村民税課税・課税所得380万円未満 (年収約770万円) |
4万4,400円(世帯) | |
| 世帯全員が市町村民税非課税 | 2万4,600円(世帯) | |
| 世帯全員が市町村民税非課税かつ 合計所得金額80万円以下 |
2万4,600円(世帯) 1万5,000円(個人)※ |
|
| 生活保護を受給している人等 | 1万5,000円(世帯) | |
※1か月の世帯単位の介護費用が2万4,600円以下でも、個人の介護費用が1万5,000円を超えると高額介護サービス費が払い戻しされる
年収約770万円未満の世帯は1か月4万4,400円が上限、市町村民税非課税の世帯は2万4,600円が上限です。
医療費用と介護費用の合計が高額になった場合は「高額介護合算療養費」
「高額介護サービス費」と似た仕組みで、医療費には1か月の医療費用が所定の限度額を超えると超過分が払い戻しされる「高額療養費制度」があります。
両制度は医療費用や介護費用の経済的負担を抑えるためのものですが、医療と介護が両方必要な場合やそれぞれが長期間続くと負担は大きくなります。
このようなケースで役に立つのが「高額介護合算療養費」という仕組みです。
高額介護合算療養費とは?
毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額が所定の基準額を超えると、超過分は「高額介護合算療養費」として払い戻しされます。
所定の基準額は、年齢と所得区分によって次の通りです。
高額介護合算療養費の基準額(70歳未満)
表は横にスライドできます
| 所得区分 | 基準額(1年) | |
| 「標準報酬月額83万円以上」または 「報酬月額81万円以上」 |
212万円 | |
| 「標準報酬月額53万~79万円」または 「報酬月額51万5千円以上~81万円未満」 |
141万円 | |
| 「標準報酬月額28万~50万円」または 「報酬月額27万円以上~51万5千円未満」 |
67万円 | |
| 「標準報酬月額26万円以下」または 「報酬月額27万円未満」 |
60万円 | |
| (低所得者)被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 34万円 | |
高額介護合算療養費の基準額(70歳以上)
表は横にスライドできます
| 所得区分 | 基準額(1年) | |
| 「標準報酬月額83万円以上」または 「報酬月額81万円以上」 |
212万円 | |
| 「標準報酬月額53万~79万円」または 「報酬月額51万5千円以上~81万円未満」 |
141万円 | |
| 「標準報酬月額28万~50万円」または 「報酬月額27万円以上~51万5千円未満」 |
67万円 | |
| 「標準報酬月額26万円以下」または 「報酬月額27万円未満」 |
56万円 | |
| (低所得者)被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 31万円 | |
| 収入が年金のみの場合、1人暮らしで約80万円以下、 2人世帯で約160万円以下等 |
19万円 | |
70歳未満で「標準報酬月額26万円以下」または「報酬月額27万円未満」の人は、年間の医療費用と介護費用の自己負担額合計は最大 60万円に抑えられます。
介護費用に関するよくある質問
ただし、これらはあくまで平均値であり、地域や施設の種類、サービス内容によって大きく差があります。中には高額な施設を利用している方もいるため、平均額がやや高めに出ている可能性もあります。
有料老人ホームなどの施設介護と比べると、約2.5倍ほど費用を抑えられる計算になります。
老人ホームの費用は、施設の種類や部屋のタイプによって異なります。例えば、特別養護老人ホーム(特養)の場合、要介護5の方が多床室を利用すると約10.7万円/月、ユニット型個室では約14.4万円/月が目安です。
これには、施設サービス費(1割負担)、居住費、食費、日常生活費が含まれます。ただし、所得に応じた減額措置があるため、実際の負担額は異なる場合があります。詳細は各施設や自治体に確認するとよいでしょう。
※参考:サービスにかかる利用料 | 厚生労働省
介護費用の負担が重いと感じる場合は、公的な支援制度の活用を検討しましょう。たとえば、
-
高額介護サービス費制度
-
高額介護合算療養費制度
-
医療費控除
などがあります。これらの制度は、所得や介護の状況に応じて利用できるものが異なるため、まずは自治体やケアマネジャーに相談し、自分が該当する制度を確認してみてください。
まとめ
今回は、「介護費用は平均いくらかかる?」「もしも介護費用が払えなかったらどうすればいい?」と不安を抱えている人に向けて、介護費用の相場(平均額)について詳しく解説しました。
まず、覚えておきたい介護費用の平均額は以下の通りです。
介護費用の相場
- 初期費用:47万円
- 毎月の介護費用:9.0万円(在宅介護は5.2万円、施設利用の場合は13.8万円)
- 介護期間:4年7か月(55か月)
- 介護費用の総額:約540万円
介護費用が高額になった場合には、「高額介護サービス費」や「高額介護合算療養費」を利用することで、負担を一定額に抑えることができます。
ただし、これらの制度を利用するには申請が必要ですので、手続きを忘れずに行いましょう。

編集部