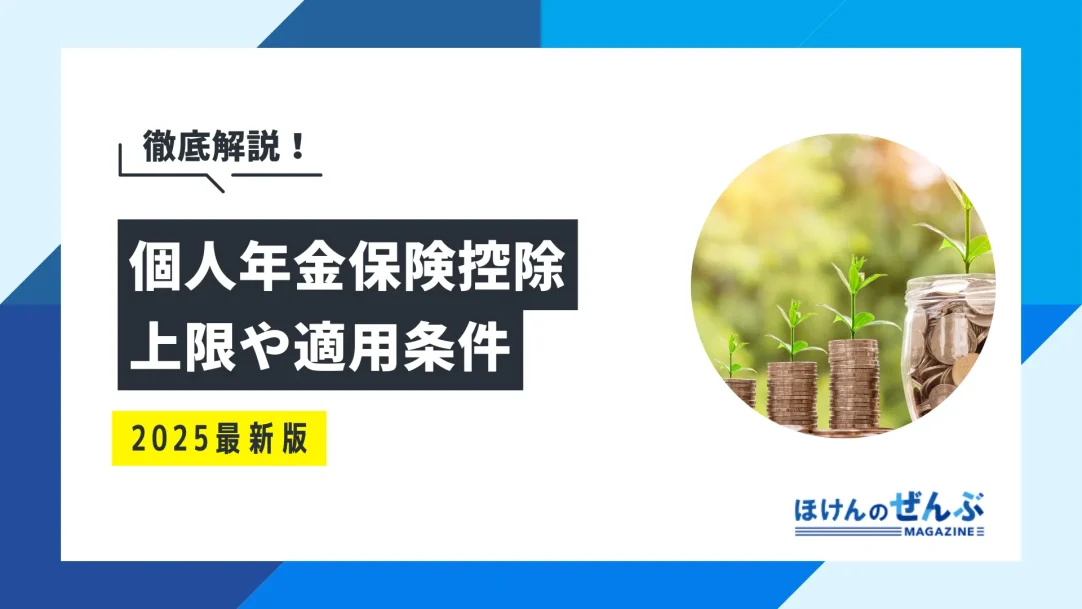銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

個人年金保険料控除とは、自分が支払った年金保険料を税金から差し引いてもらう制度で、年末調整や確定申告の手続きを通じて利用されます。
個人年金保険料控除を利用すると、税金の負担が減り、老後の資金準備に役立てられます。しかし、「控除でいくら税金が戻るのか」「控除の上限はいくらなのか」「利用するための条件は何か」など、疑問に思う方も多いでしょう。
そこで本記事では、個人年金保険料控除の適用条件や計算方法、上限について徹底解説します。

この記事のポイント
- 個人年金保険料控除とは、加入している個人年金保険に支払った年間の保険料を、その年の所得から差し引くことで所得税・住民税の節税効果を得られる制度のことです。
- 控除される金額は新制度の場合、所得税は最大4万円、住民税は最大2万8,000円となっています。
- 控除を活用するためには「年金受取人が被保険者と同一人であること」「保険料の払込期間が10年以上であること」など、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 個人年金保険のメリットを最大限活かすためにも、分からないことがあれば保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」で専門家に相談しましょう。

この記事は5分程度で読めます。
個人年金保険料控除とは
個人年金保険料控除は、加入している個人年金保険に支払った保険料を、所得税や住民税から差し引いて節税効果を得るための制度です。
この控除を受けることで、税負担が軽減され、将来の年金を準備しながら、現在の税金を抑えることができます。

編集部
個人年金保険料控除の条件
個人年金保険料控除を受けるためには、その保険に「個人年金保険料税制適格特約」を付加する必要があります。

編集部
個人年金保険料税制適格特約を付加するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
個人年金保険料税制適格特約を付加するために必要な条件
- 年金の受取人が契約者またはその配偶者であること
- 年金受取人が被保険者と同一人物であること
- 保険料の払込期間が10年以上であること
- 確定年金または有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降であり、かつ受取期間が10年以上であること
特約を付加するためには、契約者、被保険者、年金受取人が特定の条件を満たす必要があります。特に契約者が夫の場合、次の2パターンに限られます。
| 個人年金保険料税制適格特約を付加できるパターン | |||
|---|---|---|---|
| 契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 備考 |
| 夫 | 夫 | 夫 | 夫自身が契約し、保険金も年金も受け取るパターン |
| 夫 | 妻 | 妻 | 夫が契約し、妻が保険の対象・年金を受け取るパターン |
また個人年金保険料税制適格特約には、次のような注意点があります。
個人年金保険料税制適格特約の注意点
- この特約は単独で解約することはできません。
- 特約を付加した後に、契約内容を変更して条件を満たさない場合、特約が無効になることがあります。
- 年金額の減額などによる返戻金は契約途中で受け取れず、年金受取開始日以降に所定の利息とともに増額される仕組みです。
以上の注意点を確認した上で、特約を付加することを検討してください。
個人年金保険料控除の上限
個人年金保険料控除の上限額は、所得税・住民税の税種や新旧制度によって異なります。以下の表に示した通り、保険料の金額に応じて控除額が決まります。
| 個人年金保険料控除の上限 | ||
| 税種 | 年間保険料 | 控除額 |
| 所得税(新制度) | 8万円超〜 | 4万円 |
| 住民税(新制度) | 5万6,000円超〜 | 2万8,000円 |
| 所得税(旧制度) | 10万円超〜 | 5万円 |
| 住民税(旧制度) | 7万円超〜 | 3万5,000円 |
繰り返しになりますが、控除額の限度額は一般生命保険料控除や介護医療保険料控除とも同じです。
控除額の具体例
例えば、平成25年に加入した個人年金保険の年間保険料が9万円の場合、所得税に対する個人年金保険料控除額は4万円となります。
個人年金保険料控除の計算方法
控除額は生命保険料控除の種類別にそれぞれ同じです。
ただし所得税と住民税、新制度と旧制度で異なるため、それぞれを表でまとめていきます。
新制度の所得税の個人年金保険料控除額の計算方法
| 年間保険料 | 個人年金保険料控除の金額 |
| 2万円以下 | 保険料全額 |
| 2万円超〜4万円以下 | 保険料✕1/2+1万円 |
| 4万円超〜8万円以下 | 保険料✕1/4+2万円 |
| 8万円超〜 | 一律4万円 |
| 3種類の合計控除額 (上限額) |
12万円 |
新制度の住民税の個人年金保険料控除額の計算方法
| 年間保険料 | 個人年金保険料控除の金額 |
| 1万2,000円以下 | 保険料全額 |
| 1万2,000円超〜3万2,000円以下 | 保険料✕1/2+6,000円 |
| 3万2,000円超〜5万6,000円以下 | 保険料✕1/4+1万4,000円 |
| 5万6,000円超〜 | 一律2万8,000円 |
| 3種類の合計控除額 (上限額) |
7万円 |
そして旧制度の控除額は、次の表のようになります。
旧制度の所得税の個人年金保険料控除の計算方法
| 年間保険料 | 個人年金保険料控除の金額 |
| 2万5,000円以下 | 保険料全額 |
| 2万5,000円超〜5万円以下 | 保険料✕1/2+1万2,500円 |
| 5万円超〜10万円以下 | 保険料✕1/4+2万5,000円 |
| 10万円超〜 | 一律5万円 |
| 3種類の合計控除額 (上限額) |
10万円 |
旧制度の住民税の個人年金保険料控除の計算方法
| 年間保険料 | 個人年金保険料控除の金額 |
| 1万5,000円以下 | 保険料全額 |
| 1万5,000円超〜4万円以下 | 保険料✕1/2+7,500円 |
| 4万円超〜7万円以下 | 保険料✕1/4+1万7,500円 |
| 7万円超〜 | 一律3万5,000円 |
| 3種類の合計控除額 (上限額) |
7万円 |
それぞれの控除額や計算式を覚える必要はありません。ただこちらの表をいつでも確認できるようにしておくと、すぐに計算できて便利ですよ。
個人年金保険料控除でいくら戻る?【シミュレーション】
シミュレーションの条件※
- 加入保険商品:個人年金保険(確定年金)
- 契約者・被保険者・年金受取人:A氏(30歳・男性・年収450万円・所得税率20%・住民税率10%)
- 年金受取期間:10年
- 保険料払込期間:30年(60歳満了)
- 年金受給開始時期:60歳
- 年金額:60万円(月5万円・合計600万円)
- 月額保険料:1.5万円
※新制度:平成24年以後の契約
以上の場合の、A氏の控除額は、次のように計算できます。
A氏の個人年金保険料控除額
- 年間保険料:1.5万円×12ヶ月=18万円
- 個人年金保険料控除額・所得税:4万円
- 個人年金保険料控除額・住民税:2万8,000円
- 税金の控除額・所得税:4万円×0.2=8,000円
- 税金の控除額・住民税:2万8,000円×0.1=2,800円
- 税金の控除額合計:10,800円
- 年間保険料に対する割合:6%
- 保険料払込期間の税金控除額:32万4,000円

編集部
個人年金保険料控除を受ける方法は?
年末調整で申告する(会社員・公務員)
会社員や公務員が個人年金保険料控除を受けるためには、年末調整で申告を行う必要があります。
申告時には、保険会社が発行する生命保険料控除証明書を「給与所得者の保険料控除申告書」に添付し、勤務先に提出します。
もし年末調整で申告を忘れてしまった場合や、給与収入が年間2,000万円を超えて年末調整ができない場合は、確定申告を行うことで個人年金保険料控除を利用することが可能です。
確定申告で申告する(自営業者)
自営業者が個人年金保険料控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
申告時には、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付し、住所地を管轄する税務署に提出します。
e-Taxで確定申告を行う場合、生命保険料控除証明書の添付は省略可能です。ただし、証明書は5年間保存する必要があります。
個人年金保険料控除に関するよくある質問
個人年金保険料控除を受けると、所得税や住民税の負担が軽くなり、将来の老後に備えられます。
所得税や住民税は、個々の所得に応じて計算される税金です。個人年金保険料控除を利用すると、課税対象となる所得(課税所得)が減ります。その結果、所得税や住民税の支払い額が減少し、負担が軽くなるのです。
まとめ
本記事では、個人年金保険料控除の適用条件や計算方法、上限など基本的な情報をまとめてご紹介しました。
個人年金保険料控除とは、加入している個人年金保険(一定の条件あり)に支払った年間の保険料を、その年の所得から差し引くことで所得税・住民税の節税効果を得られる制度のことでした。
個人年金保険料控除を活用すれば、他の控除枠とも組み合わせて、長期間で見れば大きな節税効果が期待できます。ただし、控除を利用するには一定の条件を満たすことが必要です。
ここを理解していないと、個人年金保険料控除の枠を全く活用できず、節税効果が落ちてしまいます。

編集部
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。 ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。 また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

生命保険の業界歴10年。年間500世帯の相談実績。 社会保険・税金の効率化、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、不動産投資と幅広い分野に精通。