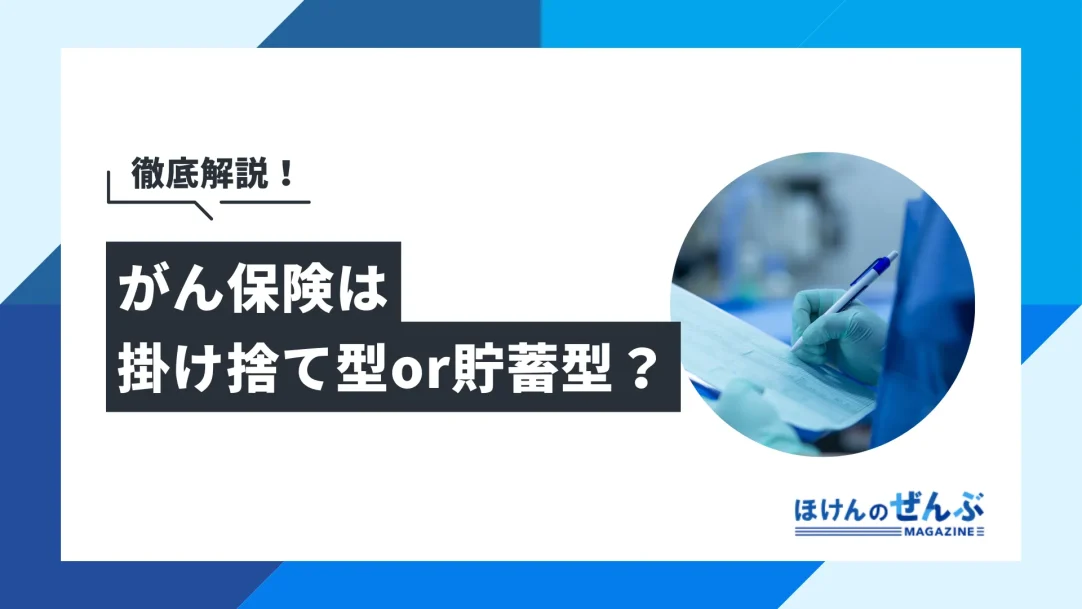銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

がん保険には掛け捨て型と貯蓄型の2種類があり、「どちらを選べばいいのか分からない」と迷っている方は多いのではないでしょうか。
多くのがん保険は解約返戻金がない「掛け捨て型」が主流ですが、どちらのタイプもそれぞれメリットとデメリットがあり、どちらが優れているかを一概に判断するのは難しいです。
この記事では、特に「掛け捨て型」のがん保険に焦点を当て、その特徴やメリット・デメリット、貯蓄型保険との違いについて徹底解説します。

編集部

この記事の要点
- 掛け捨て型のがん保険は、保険料が安く広範な保障が得られますが、保険料は戻ってこないため、貯蓄機能がありません。
- 一方、貯蓄型のがん保険は、万が一の保障と将来の備えが同時にできますが、掛け捨て型よりも数倍高い保険料が必要です。
- 掛け捨て型のがん保険は、一定期間だけがんのリスクに備えたい方や保険料をできるだけ抑えたい方におすすめです。
- がん保険を選ぶ際は、保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」で専門家と相談してみましょう。専門家があなたのニーズに合わせて40社以上の保険商品から最適な保険をご提案!相談料は何度でも無料です。

この記事は5分程度で読めます。
こちらの記事も読まれています
※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会や国税庁等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
第三分野商品(疾病または介護を支払事由とする商品)に関するガイドライン
募集文書等の表示に係るガイドライン
広告等に関するガイドライン
目次
がん保険の掛け捨て型と貯蓄型とは?
掛け捨て型のがん保険は保障に特化している
掛け捨て型のがん保険とは、解約した時に解約返戻金や満期金などを受け取れない、あるいは受け取ることができてもごくわずかな金額の保険のことです。

編集部
掛け捨て型のがん保険は解約返戻金が返ってくる貯蓄性の高い保険に比べて、保険料が安くなるのが特徴です。
貯蓄型のがん保険は解約返戻金が受け取れる
貯蓄型の保険は、解約した場合に払い込んだ保険料の一部を解約返戻金として受け取れるため貯蓄型と呼ばれます。
給付金を受け取る理由が全くないとしても解約返戻金という形で一部を受け取れるため、保険料が全て無駄になるということがありません。

編集部
掛け捨て型がん保険のメリット・デメリット
掛け捨て型のがん保険のメリット
掛け捨て型がん保険のメリットとしては、以下の3つが挙げられます。
掛け捨て型のがん保険メリット
貯蓄型と比べて保険料が安い
掛け捨て型がん保険の最大のメリットは、貯蓄型よりも保険料が割安に抑えられることです。
例えば、子育て世代は子どもの教育費や住宅ローンなどの負担が大きい時期なので、がん保険だけでなく家計のあらゆる出費は最小限にしたいと思うでしょう。

編集部
小さな保険料で大きな保障が得られる
掛け捨て型のがん保険は、保険料の負担を最小限にしつつ、がんに対して大きな保障を得られます。

ただし、注意点としては貯蓄性能がない分、将来の備えは自分の手で行わなければいけません。
浮いたお金を趣味や娯楽費に使うこともできますが、若いうちから老後を見据えて資産形成を進めておくべきです。
保険の見直しが容易
掛け捨て型のがん保険は、保険の見直しがしやすいのも大きなメリットです。
医療技術の進歩に伴い、保険商品も日々進化しており、時代に合った保障内容を取り入れることができます。
以前のがん保険では入院時に数日の免責期間が設けられているのが一般的でした。しかし、近年は入院日数が短縮され※、通院治療が増えているため、免責期間があると給付対象にならないまま退院してしまうケースも増えてきました。
また、かつては「がんと診断された際の一時金」を重視する保険が主流でしたが、現在は入院1日目から保険金を受け取れる商品が一般的です。

編集部
掛け捨て型は解約返戻金がないことがデメリットと捉えられがちですが、元本割れを気にせず、柔軟に最新の保険へ移行できる点は大きな利点といえるでしょう。
※出典:厚生労働省「令和5年(2023)患者調査の概況」
掛け捨て型がん保険のデメリット
掛け捨て型はメリットが大きい保険ですが、もちろんデメリットもあります。契約前に以下のデメリットを把握しておきましょう。
掛け捨て型のがん保険デメリット
途中で解約しても解約返戻金がない
掛け捨て型の保険料が割安なのは、解約返戻金や還付給付金が受け取れないことによります。

編集部
「貯蓄と保障を一緒に準備したい」というニーズには対応できないため、加入者自身が
- 別の貯蓄型の保険に加入する
- 将来を見据えて自発的に預貯金・投資を行う
等といったアクションが必要です。
保険期間が決まっている商品がある
ひとくちに掛け捨て型といっても、保険によって保険期間はさまざまです。終身タイプのほか、5年・10年など定期タイプの保険もあります。
定期タイプの保険の場合、保険期間満了時に更新するか解約して他の保険に切り替えるかを決める必要があります。
更新タイプの保険料は終身よりは保険料が安めに設定されていますが、更新を重ねるごとに年齢に合わせて保険料が上がるのが一般的です。
最終的には終身型よりも保険料が割高になる可能性があることは知っておきましょう。
こちらの記事も読まれています
貯蓄型のがん保険のメリット・デメリット
貯蓄型のがん保険のメリット
貯蓄型のがん保険のメリット
解約返戻金を受け取れる
貯蓄型のがん保険では、保険を途中で解約した場合、解約返戻金を受け取れることが一般的です。保険料の一部が積み立てられ、解約時にその積立金が返戻金として支払われます。
保障と貯蓄の両方を得たい人に向いている保険といえるでしょう。
1つの保険で保障と貯蓄がセットで得られる
貯蓄型のがん保険を選ぶことで、がんの保障と資産運用を1つの契約で実現できます。
保険料を積み立てることで、自動的に貯蓄が進むため、計画的にお金を貯めることが難しい人にも最適です。
契約者貸付を利用できる
貯蓄型のがん保険では、契約者貸付を利用できます。契約者貸付とは、解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りられる制度です。
自分自身で積み立ててきたお金を利用するため、貸付けを受けるのにも厳しい審査は必要ありません。
また、契約者貸付を利用しても保険契約は継続し、保障もそのまま受けられます。保険を解約しなくても資金調達できるため、急な支出にも対応しやすいでしょう。

編集部
自動振替制度を利用できる
貯蓄型のがん保険では、自動振替制度を利用できます。この制度は、契約者が保険料を支払えない場合に、解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えてくれるものです。(※ただし、立て替えた金額には利息が付き、後に解約するとその金額と利息が解約返戻金から差し引かれます。)
急な支出で口座残高が不足し、保険料が支払えない場合でも、自動振替制度を活用すれば保険契約を維持できます。

編集部
貯蓄型のがん保険のデメリット
貯蓄型のがん保険のデメリット
掛け捨て型よりも保険料が高い
貯蓄型のがん保険は、掛け捨て型に比べて保険料が高くなるのがデメリットです。
途中解約すると貯蓄性の高さが発揮できない
貯蓄型の解約返戻金は、長く契約することで少しずつ金額が大きくなっていきます。
短期間で解約してしまった場合、高い保険料を支払うことによって得られる貯蓄型のメリットが十分に発揮されません。
高い返戻率が期待できない
貯蓄型と聞くと、高い貯蓄性がメリットになると考えるでしょう。しかし、がん保険の場合は貯蓄型といっても返戻率はそこまで高くありません。
長く加入することで解約返戻金が支払保険料を上回る保険としては終身保険・養老保険・学資保険などが有力ですが、これらと比較して解約返戻率は低く設定されるのが一般的です。
保険の見直しがしにくい
貯蓄型のがん保険は、解約のタイミングによって元本割れのリスクがあるため、新しい保険への切り替えが難しい場合があります。
特に契約から短期間で中途解約すると、支払った保険料よりも少ない解約返戻金しか受け取れないため、損失が発生しやすくなります。

編集部
掛け捨て型と貯蓄型のがん保険、どちらを選べばいい?
がん保険における掛け捨て型と貯蓄型の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 貯蓄型 | 掛け捨て型 |
|---|---|---|
| 保険料 |
△ |
○ |
| 解約返戻金 | ○ 商品次第であり |
× なし |
| 満期保険金 | ○ 商品次第であり |
× なし |
| 特徴 | 貯蓄性があり、契約者貸付が使える | 保険料が安く、見直しがしやすい |
| 注意点 | 早期解約すると返戻金がほとんどない | 更新時に保険料が上がる場合がある |
| 加入の目的 | 貯蓄と保障を両立したい人 | 保険料を抑えたい人、保障を柔軟に見直したい人 |
上記から分かるように、掛け捨て型と貯蓄型のがん保険、どちらが優れているかは一概に言えるものではありません。
掛け捨て型も貯蓄型も基本的な保障内容は大きく変わらないため、個々のライフスタイルや予算、将来の資金計画によって選択すべきでしょう。

編集部
掛け捨て型のがん保険がおすすめな人の特徴
では、掛け捨て型のがん保険はどのような人におすすめなのでしょうか?以下の項目に、どれくらい当てはまるか確認してみてください。
掛け捨て型のがん保険がおすすめな人
一定期間だけがんのリスクに備えたい人
掛け捨て型は契約期間を設定できるため、将来の特定の期間においてがんの発症リスクに備えるのに適しています。
例えば、子供の学費をまかなうために特定の期間内に給付金が必要な場合や、住宅ローンの返済期間中にリスクをカバーしたい場合におすすめです。

編集部
なるべく保険料を安く抑えたい人
掛け捨て型は通常、終身型よりも保険料が安い傾向にあります。
リーズナブルな保険料でがんのリスクに備えられるため、若い世代や子どもの教育費や生活費で支出の多い世代でも利用しやすいでしょう。
一時金の受け取りを希望する人
掛け捨て型の場合は、がんが発症した場合に一括で給付金が支払われます。そのため、がん治療や生活費用の急な支出に対応できるか不安な人におすすめです。
また、一時金の利用方法は自由であり、がんの治療費用だけでなく、家計の支えや追加の医療機器購入などにも活用できます。

編集部
他の生命保険と組み合わせてリスクに備えたい人
一般的に、生命保険は死亡時や入院時に給付金が支払われるものであり、がん以外の疾病や事故に対する補償が含まれています。
一方、がん保険はがんの発症に特化した給付金を提供します。したがって、両者を組み合わせることで、がんに限らず幅広いリスクに備えることが可能です。
掛け捨て型のがん保険は比較的安い保険料で利用でき、特定の契約期間内のリスクに備える柔軟性があります。そのため、他の生命保険との組み合わせると、効果的に包括的な保障を得られます。
掛け捨て型のがん保険を選ぶ際のポイント
掛け捨て型のがん保険を選ぶ際には、どのような点に気を付けて選べばよいのでしょうか。
以下では、掛け捨て型のがん保険の選び方をご紹介します。ぜひ参考にしてください。
掛け捨て型のがん保険を選ぶ際のポイント
保険料の安さだけを求めない
掛け捨て型がん保険を選ぶ際、保険料の安さを重視する方は多いでしょう。同じ保障内容であれば保険料が安い方が魅力的に感じられます。
そのため、単に保険料が安いことだけを基準に選ぶのは注意が必要です。
掛け捨て型がん保険を選ぶ際は、保障内容が自分に必要な範囲をカバーしているか、また給付金の支払い条件が納得できるものかをしっかり確認するようにしましょう。
契約更新時は見直しのチャンス
掛け捨て型がん保険は、保障期間が10年や20年といったように、一定期間に限定されている「定期型がん保険」のこともあります。
定期型がん保険は、保険期間満了時に契約更新手続きをすることが多いです。
医療の進歩により、がんの治療法には日々新しい技術が取り入れられています。それに合わせて、がん保険の保障内容も変更されているので、10年や20年前のがん保険とは保障内容が大きく変わっている可能性があります。
貯蓄型がん保険は、解約返戻率が小さくなってしまうということもあり、簡単に解約することが難しいですが、掛け捨て型がん保険であれば解約返戻金を気にせずに最新のがん保険に乗り換えることができます。
契約更新ができないこともあるので終身型がおすすめ
掛け捨て型のがん保険に加入している場合、契約更新の手続きをしたいと思っても、一度がんに罹患してしまっていたり、健康状態が良好でなかったりする場合は、契約更新できない可能性があります。
がんは、高齢になるにつれ罹患率が高くなっていく疾病です。

編集部
しかし、一度がんに罹患してしまった、または健康状態が良好でなくなってしまったという場合は更新ができず、がん保障が付けられない可能性があります。
必要な年代に必要な保障が得られなくなる可能性があるため、高齢期のがん保障にもしっかりと備えた方は、終身型のがん保険を検討することをおすすめします。
まとめ
今回は、掛け捨て型のがん保険にスポットを当てて、特徴やメリット・デメリット、保険料の相場をご紹介しました。
掛け捨て型のがん保険とは、解約時に解約返戻金や満期金などを受け取れない保険のことです。手頃な保険料で広範な保障を手に入れられる反面、保険料が戻ってこないため貯蓄性がないといった特徴があります。
これらの特徴から、掛け捨て型のがん保険は一定期間だけがんのリスクに備えたい方や、なるべく毎月の保険料を安く抑えたい方などにおすすめです。
加入の際は、保険料の安さだけでなく必要な保障がカバーされているか、保障内容とともに給付金の支払い条件もしっかり確認して選びましょう。

編集部
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。 ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。 また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

愛知県出身。社会保険・税金の効率化、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)の相談を得意とする。