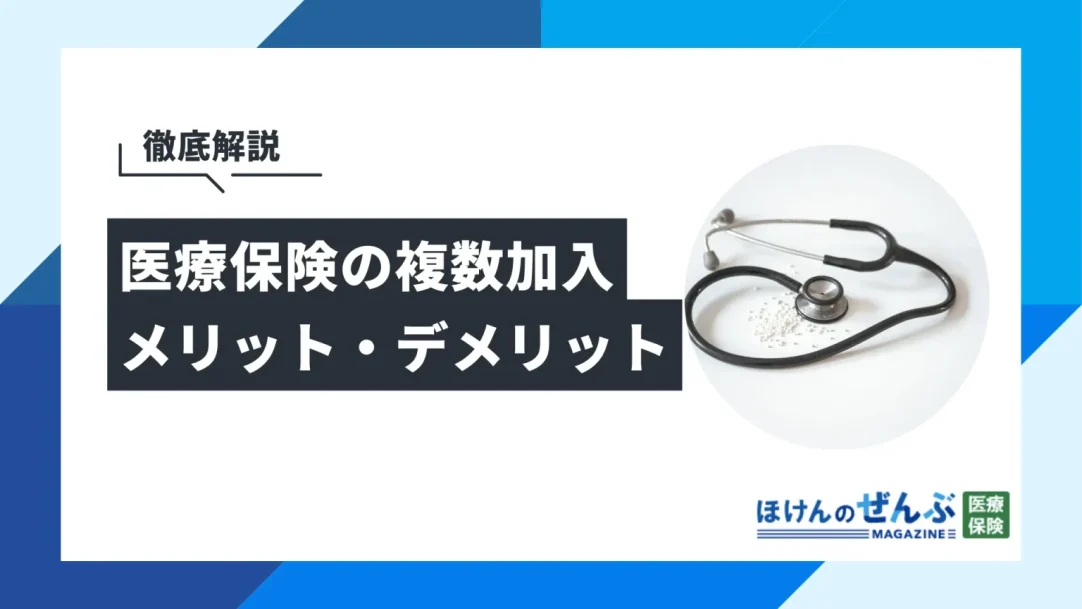銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

これから医療保険を検討する方の中には、医療保険は複数加入できるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、似た保障内容でも医療保険に複数加入は可能です。
しかし、「複数の医療保険に加入するメリットは?」「保険金には上限があるの?」といった疑問があるかもしれません。
そこで本記事では、医療保険に複数加入するメリット・デメリット、注意点について徹底解説します。

この記事の要点
- 医療保険を複数加入すると、条件を満たせば複数の保険から給付金を受け取ることが可能です。ただし、保険料の負担増や手続きの煩雑さといったデメリットもあるため注意が必要です。
- また、職業や年齢によって給付金の上限が設けられる場合があるため、事前の確認を忘れないようにしましょう。
- 医療保険選びに迷ったら、保険相談窓口「ほけんのぜんぶ」を活用するのがおすすめです。40社以上の保険商品から専門家があなたに最適なプランを提案してくれるので、効率的に納得のいく保険を選べます。

この記事は5分程度で読めます。
こちらの記事も読まれています
金融商品取引法
募集文書等の表示に係るガイドライン
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
第三分野商品(疾病または介護を支払事由とする商品)に関するガイドライン
広告等に関するガイドライン
医療保険に複数加入することは可能?
結論から言うと、医療保険に複数加入することは可能です。
医療保険は医療費の金額には関係なく、契約内容に応じた給付金を受け取れるタイプの保険です。
「複数の保険契約はしてはいけない」「複数契約すると給付金額が減額される」このような内容は約款には記載されていません。

編集部
たとえば入院日額5,000円を受け取れる医療保険に3つ加入している場合、1日1万5,000円を受け取れる計算になります。
別々の保険会社でも複数加入できる
医療保険への複数加入は、同じ保険会社に限った話ではありません。以下のどちらのパターンでも複数契約できます。
- 同じ保険会社で別々の医療保険に複数加入
- 異なる保険会社で複数の医療保険に加入
がん保険も複数加入できる
医療保険の一種であるがん保険でも、複数加入することは可能です。
たとえば…
- 診断給付金が複数回受け取れるAがん保険
- 入院給付金が手厚いBがん保険
がん保険も医療保険と同じく、保険ごとに強みが異なります。複数の保険を組み合わせることで、それぞれのメリットを活かすことができます。

編集部
特に重要なのは、診断給付金が複数回受け取れるかどうかです。
がんは転移や再発のリスクがあるため、現在加入している保険が1回のみの給付だと不安が残ります。その場合、別の保険を追加することも検討してみましょう。
複数の保険に加入していても高額療養費が使える
日本の公的保険制度には「高額療養費制度」があります。1ヶ月の医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分の金額が払い戻される制度です。
また、直近12ヶ月以内に3回以上の高額療養費を利用すると、4回目以降は多数該当として1ヶ月ごとの上限額がさらに安くなることもあります。

編集部
70歳未満の高額療養費・多数該当の上限は以下のとおりです。
表は横にスライドできます
|
所得区分
|
自己負担限度額
|
多数該当
|
|---|---|---|
|
① 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%
|
140,100円
|
|
② 区分イ (標準報酬月額53万〜79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
|
93,000円
|
|
③ 区分ウ (標準報酬月額28万〜50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
|
44,400円
|
|
④ 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円
|
44,400円
|
|
⑤ 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円
|
24,600円
|
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
引用元:全国健康保険協会|高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
医療保険に複数加入するメリット
医療保険に複数加入するメリットは主に4つあります。
受け取れる給付金が増える
複数の医療保険に加入することで、それぞれの保険から給付金を受け取ることができます。これにより、1つの支払い事由に対して受け取れる給付金額が増えます。
例えば、以下のケースを考えてみましょう。
- A医療保険で入院給付金1日につき1万円
- B医療保険で入院給付金1日につき5,000円
もし10日間入院した場合、A医療保険だけに加入していれば、10日分で10万円の給付金を受け取れます。しかし、AとBの両方に加入していれば、15万円(A:10万円+B:5万円)を受け取ることができるのです。
複数の医療保険のメリットを享受できる
1つの医療保険によって備えたい保障の全てが得られない場合でも、複数の医療保険に加入すればそれぞれの保険の強みを享受できます。

編集部
この組み合わせであれば、入院と通院のどちらが長引いても安心できるでしょう。
たとえば医療保険ではあらゆる病気・ケガをまんべんなくフォローできますが、特定の病気への備えは弱いと感じることもあります。
ポイント
- がんに手厚く備えたい場合には医療保険に加えて「がん保険」への追加加入がおすすめです。
- 診断給付金などが受け取れるがん保険に加入することで、がんに手厚く備えられます。
逆にがん保険の「がん以外の疾病は対象外」という欠点は、医療保険の存在でカバーできるのです。
相談する人が増える

保険会社が破綻した場合のリスクが小さくなる
保険は複数の保険会社に分散して契約することで、万が一保険会社が破綻した場合のリスクを分散できます。
破綻の可能性は低いと思われがちですが、過去には本当に保険会社が倒産した実例もあります。

編集部
さらに問題なのは、「医療保険に新たに加入できなくなる」ことです。
保険金額が減少し、保障が不十分だと感じた場合、新たに加入を考えるかもしれません。しかし、すでに病気になっている場合、加入が難しくなることもあります。
保険会社の破綻が気になる方は、契約を分散させることで安心感を得られるでしょう。
医療保険に複数加入するデメリット
医療保険に複数加入するとさまざまなメリットがある一方で、デメリットもあります。検討する際は、以下の点についても理解しておきましょう。
保険料負担が増える
当たり前ではありますが、複数の医療保険に加入するとそれだけ保険料の負担が増えます。保険料の支払いが高くなることで、日常生活で我慢を強いられるようになるのは本末転倒です。

編集部
2つ目以降に加入したい保険を「上乗せしたい保障をベース」で決めてしまうと、保険料はどうしても毎月支払える金額をオーバーしがちです。
先に毎月支払える保険料の最大金額を決めておくと、決めた保険料の範囲内で最大限の保障が得られる組み合わせを検討できます。家計を圧迫することなく、合理的な保障を受けられるでしょう。
保障内容が重複する場合がある
複数の医療保険に加入したとしても、全ての保険で受けられる保障がまったく重複しないとは限りません。

編集部
複数加入によって得られる給付金以上の治療費がかかった場合は複数の保険に加入した意味があるでしょうが、もし1社の医療保険で間に合う程度の金額だったら2社目以降の保険料が無駄になります。
ポイント
- 保険相談窓口で専門家に相談しながら、1日に必要になる入院費用・通院費用などをシミュレーションしてみましょう。
- 1社の保険と公的保険でカバーできることが分かれば、無理に複数の保険を契約する必要はありません。
手続きや管理が複雑になる
複数の医療保険に加入する際は、それぞれの保険で必要な手続きや健康状態の告知が発生し、契約成立までに時間や手間がかかります。
さらに、保険加入後は状況に応じて複数の保険会社に請求を行う必要があり、どの保険を利用するか常に把握しておくことが求められます。
場合によっては、主治医の診断書も保険会社ごとに用意する必要があり、手間が増えます。
例えば、「A保険はこの状況で、B保険はあの状況で」といったように、状況ごとに請求先を把握し整理することが重要です。

要注意!医療保険に複数加入しても給付金を受け取れない場合
以下のケースの場合、医療保険に複数加入しても給付金を受け取れない可能性があります。
加入者の年齢や職業に制限がある場合
全ての医療保険に加入できた場合でも、保険金・給付金の全額を受け取れるわけではありません。
何社もの保険に加入して全額を受け取れると、保険金目当ての事件が発生するためです。
ポイント
- 加入者の「年齢」「職業」「収入」などによって、加入できる保険や保険金・給付金には上限が定められます。
- たとえば「高所作業員」「トラック運転手」など、危険度が高いとされる職業に関しては受け取れる保険金・給付金が少ない傾向にあります。
実際にそれだけの保険金を受け取れるのかについては個人ごとに異なるため、加入を決めてしまう前に保険会社に連絡して確認しましょう。
必要な書類が揃わない場合
医療保険において、入院給付金を請求する場合は会社所定の様式に沿って、医師の診断書が必要になります。
診断書の費用は病院によっても異なりますが、高い病院では1万円程度が相場になっています。
ポイント
- もし費用がかかりすぎる等の理由で診断書を用意できない場合は、診断書を提出できない保険会社の医療保険の給付を受けることはできません。
- ただし、保険会社によっては条件を満たした場合に原本ではなく、診断書のコピーの提出でも可としているところもあります。
- また、診断書がなくても領収証があれば請求できるケースもあります。
加入している保険によっては1枚だけ診断書を発行すれば、全ての医療保険を請求できる場合もあります。
まとめ
今回は「医療保険は複数加入ができるのか?」について解説しました。
同じ保険会社の別の医療保険でも、異なる保険会社の医療保険でも、支払い事由に該当すればいずれの給付金も受け取ることは可能です。ただし、職業や年齢などの条件によって上限が定められることはあります。
また、複数の保険に加入することはメリットばかりではありません。当然のことながら加入した保険の数だけ保険料の支払いが必要ですし、給付金の手続きも煩雑になります。
1つの医療保険の給付金額を充実させるのと、どちらのメリットが大きいのか、加入前にきちんと把握しておきましょう。

編集部
大学卒業後、信用金庫に入社。中立的な立場でお客様目線の営業をしたいという思いから、保険代理店として独立を決意。
保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店『コミヤ保険サービス』を設立。
保険代理店の実務経験を生かして、執筆業や講師業も行う。

人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

岩手県出身。大学卒業後、銀行、外資系生命保険会社、建設業(企業再生)を経て、ほけんのぜんぶに入社。
保険業界経験歴は18年。岩手県生命保険協会副会長も務める。