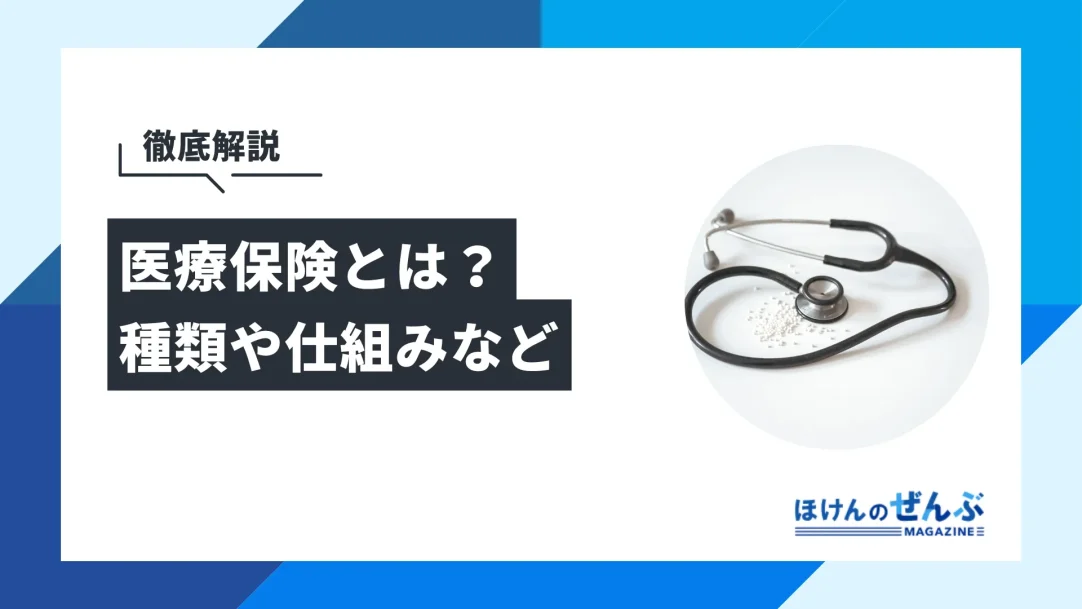銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

医療保険とは、病気やケガによる医療費の負担を軽減するための保険です。一般的には生命保険会社の商品を指しますが、病院で利用する公的医療保険も広い意味では医療保険に含まれます。
そのため、「公的医療保険と民間の医療保険の役割は?」「医療保険と生命保険の違いは?」などの疑問を持つ方もいるでしょう。
この記事では、医療保険の特徴や種類、保障内容について初心者にもわかりやすく解説します。医療保険を検討中の方や、仕組みを詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
この記事の要点
- 医療保険とは、病気やケガで発生する医療費を軽減する保険で、公的医療保険と民間医療保険の2種類に分けられます。
- 公的医療保険は日本の「国民皆保険制度」に基づくもので、全国民が医療費補助を受けられる仕組みです。ただし、差額ベッド代や先進医療費など、自己負担が必要な費用もあります。
- 民間医療保険は、こうした自己負担費用を補うための保険です。種類も多く、入院費用や特約付きの先進医療補償など、ニーズに応じた商品があります。
- 医療保険を選ぶ際は、専門家に相談することで最適な保険を見つけやすくなります。「ほけんのぜんぶ」では、40社以上の保険商品からあなたに合った保険を提案してくれます。

この記事は5分程度で読めます。
医療保険とは?
医療保険とは、病気やけがの治療に要した医療費の一部負担を保証するものです。
小さなけがならば数千円の負担で済むケースもありますが、入院や手術をした場合、数十万円から数百万円の医療費がかかるケースもあります。

編集部
医療保険には公的医療保険と私的な医療保険がある
医療保険には、次の2種類があります。
2種類の医療保険
- 公的医療保険(国民皆保険)
- 私的な医療保険
主な公的医療保険は、要件を満たす国民全員が加入する健康保険などの社会保障制度です。
一方、社会保障制度でカバーできない自己負担費用を賄うために任意で加入するのが私的な(民間の)医療保険です。

公的医療保険とは?
公的医療保険とは、国や地方公共団体による医療保障のことです。
国による主な医療保険制度は、雇用保険や労働者災害補償保険(以下、労災保険)、健康保険、介護保険、公的年金(国民年金や厚生年金)です。
国による医療保険制度
- 雇用保険:病気で仕事ができないとき、収入を保障するために「休業手当」が支給される。
- 労災保険:業務中や通勤中の病気やけがに対して、「療養補償給付」「休業補償給付」が支給される。
- 健康保険:業務災害や通勤災害以外の病気やけがなどに対して、「療養費」「高額療養費」「出産手当金」などが支給される。
- 介護保険:所定の要介護状態に対して介護サービスが提供される。
- 公的年金:所定の障害状態に対して障害年金が支給される。

編集部
地方公共団体ごとに定めた年齢以下の子どもの医療費については、自己負担分を地方公共団体が負担してくれます。
健康保険の保障内容
業務災害や通勤災害以外の病気やけがに対する公的医療保険として、よく使われるのは健康保険です。
健康保険は職業などによって加入する保険制度が異なります。
職業や年齢によって異なる保険制度
- 自営業者やその家族:国民健康保険
- 会社員やその家族:健康保険組合や協会けんぽ
- 公務員やその家族:各共済(国家公務員共済、地方公務員共済など)
- 75歳以上の人:後期高齢者医療制度
主な給付内容は次の通りです。
| 保険給付 | 給付の内容 |
| 療養費 | 治療費の7割が健康保険から給付され、自己負担は原則3割(年齢や収入で異なる) |
| 高額療養費 | 1か月の医療費が高額になり自己負担が一定の限度額を超えた場合、超過部分の還付 |
| 出産育児一時金 | 産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した時、出産費用として子ども1人あたり42万円の一時金※これ以外の医療機関で出産した時には、40.4万円。 |
| 埋葬料 | 死亡時に被保険者に生計を維持されていた人に、申請により5万円の給付金 |
| 傷病手当金 | 病気やけがで療養のため3日以上会社を休んでその間報酬がなければ、4日目以降に給与の2/3相当が支給される(最長1年6か月)※会社員や公務員のみ。自営業者には支給されない |
| 出産手当金 | 出産のため会社を休んで報酬がなければ、給与の2/3相当が支給される
※会社員や公務員のみ。自営業者には支給されない |
労災保険の保障内容
業務災害や通勤災害によって病気やけがをした場合は健康保険を使えません。

編集部
たとえば、病院の窓口で支払う医療費は健康保険が原則3割負担であるのに対し、労災保険では自己負担がありません。
注意点
ただし、対象は会社員などで自営業者は加入対象外です。
主な給付内容は次の通りです。
| 保険給付 | 給付の内容 |
| 療養(補償※)給付 | 治療費が無料(労災病院など)。治療費を支払った場合は還付金 |
| 休業(補償)給付 | 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業4日目から、休業日数などに応じて給付金を支給 |
| 障害(補償)給付 | 所定の障害が残ったとき、程度に応じて年金または一時金を支給 |
| 遺族(補償)給付 | 労災で死亡した場合、遺族に年金または一時金を支給 |
| 葬祭料(通勤災害は葬祭給付) | 労災で死亡した場合、葬儀を行う者などに一時金を支給 |
| 傷病(補償)年金 | 療養開始から1年6か月経過しても治癒(症状固定)しない場合などに年金が支払われる |
| 介護(補償)給付 | 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に給付金が支給される |
※業務災害のときは給付名に「補償」がつき、通勤災害のときはつかない。
参考:東京労働局「労災保険給付の一覧」
民間の医療保険とは?公的医療保険との違い
日本の公的医療保険制度は基本的な医療費をカバーしますが、すべての費用をまかなうわけではありません。そこで、民間の医療保険がどのように役立つのかを確認していきましょう。
公的医療保険ではカバーできない費用を補うもの
公的医療保険では、多くの医療費がカバーされますが、すべての費用に対応しているわけではありません。以下のような費用は自己負担となります。
公的医療保険でカバーされない費用
- 先進医療費
- 差額ベッド代
- 入院中の食事代や日用品費
- 家族の交通費や宿泊費など付随する費用
先進医療費は、厚生労働省が認めた高度な医療技術を使用した治療で、その技術料は全額自己負担です。
先進医療費は数十万から数百万円に及ぶこともあり、例として「陽子線治療」では約268万円、「重粒子線治療」では約314万円が必要となります※。
個室などを利用した際の差額ベッド代も自己負担で、1日あたりの平均は約6,714円※2。そのほか、入院中の食事代や日用品、付き添い家族の交通費なども保険の対象外です。

編集部
※1 出典:中央社会保険医療協議会「令和6年6月30日時点における先進医療に係る費用」
※2 出典:中央社会保険医療協議会「主な選定療養に係る報告状況」令和6年7月時点
差額ベッド代や治療費を民間医療保険でどこまでカバーできる?
公的医療保険ではカバーできない差額ベッド代や一部の治療費などについて、民間の医療保険がどのように補填できるかを具体的に見てみましょう。
例えば、1日入院して治療費が1万円、差額ベッド代が6,700円だった場合。入院給付金が日額1万円の医療保険に加入していると、以下のように補填されます。
- 治療費に対する自己負担額(3割負担の場合):1万円×30%=3,000円
- 差額ベッド代の自己負担額(全額自己負担):6,700円
- 民間医療保険からの入院給付金:1日あたり1万円
自己負担額は合計で9,700円ですが、保険から1万円の給付があるため、実質的な自己負担額は0円となります。

編集部
貯蓄を切り崩すのは限界がある
医療保険に加入しない人の中には、「医療費は貯蓄から支払うので民間の医療保険は必要ない」という人もいます。
たしかに、高額な貯蓄のある人であれば、医療費の支払いに困ることはないかもしれません。
注意点
- しかし、病気の中には治療が長引くものもあり、特にがんのように治療期間が長引き再発や転移といった可能性もある病気の場合は、長期間の療養が必要になることもあります。
- その間は仕事を休業する必要があり収入が途絶えてしまうかもしれません。
そのような状況で、貯蓄を切り崩しながら治療を続けるのは、将来の治療費や生活費への不安材料となるでしょう。また、配偶者や子どもの生活費や教育費にまで大きな影響が出る恐れもあります。
貯蓄は、医療費以外にも教育費や住宅ローンの支払いなど、他の重要な場面で必要となるケースが多いです。

編集部
民間の医療保険は大きく分けて8種類ある
公的な医療保険について説明してきましたが、次は生命保険会社などが販売する民間の医療保険についてみていきましょう。

それぞれについて詳しくみていきましょう。
1. 定期医療保険
医療保険の種類を保障期間で分類すると、「定期医療保険」と「終身医療保険」に分類できます。
定期保険の主な特徴は次の通りです。
定期医療保険の特徴
- 保障期間が満了しても更新できる。(ただし、更新には限度年齢が設定されている場合がある)
- 終身医療保険より保険料が安い。
- 更新時に保険料がアップする。
- ほとんどの商品は途中解約しても返戻金はない。

編集部
2. 終身医療保険
定期医療保険と比較して、次のような特徴があります。
終身医療保険の特徴
- 一生涯の医療保障を準備できる。
- 定期医療保険より保険料が高い。
- 商品によっては途中解約したとき返戻金がでるものもある。
今後医療保険の見直しを考えている人は、保険料が高めの終身医療保険は避けた方が良いかもしれません。

編集部
3. 掛け捨て型医療保険
医療保険の種類を解約返戻金や満期返戻金の有無で分類すると、「掛け捨て型医療保険」と「貯蓄型医療保険」に分類できます。
貯蓄型医療保険と比較して、返戻金がない分、保険料が安いのが特徴です。

編集部
保険料を一定範囲に抑えるのに適した型といえるでしょう。
4. 貯蓄型医療保険
貯蓄型医療保険の特徴
- 一定期間保険金の支払がなければ、「無事故返戻金」や「健康祝い金」などの名称で一時金が支払われるタイプのものもあります。
- 掛け捨て型医療保険と比較して保険料は高くなりますが、掛け捨てはもったいないと考える人にとっては選択肢の1つです。
ただし、貯蓄型の医療保険は販売されている商品数が少ないので、保障内容にこだわる場合、適した商品が見つからない可能性もあります。
5. 引受基準緩和型医療保険
主な告知項目
- 2年以内に病気やけがで入院したことがない、もしくは手術を受けたことがない。
- 直近5年間でがんなど特定の病気の診断を受けたことがない。
リスクの高い人でも加入できる点が大きなメリットですが、一般の医療保険と比べて保険料が高く、また保障内容に制限がある場合があります。
6. 無選択医療保険
引受基準緩和型医療保険よりも加入条件が緩和されていて加入しやすいですが、保険料はさらに高くなります。
また、無選択型医療保険の多くは、加入年齢や保障期間、保障内容(免責期間の設定)などに制限が設けられています。
7. がん保険
主な保障は次の通りです。
主ながん保障
- がん診断一時金:がんと診断された場合に一時金が支給される。
- がん入院給付金:がん治療のために入院した日数に応じて給付金が支給される。一般的に入院給付金の支給日数は無制限。
- がん通院給付金:がん治療のために通院した日数に応じて給付金が支給される。
- がん手術給付金:がん治療のために所定の手術(放射線治療を含む)を受けたときに給付金が支給される。
- がん先進医療給付金:がんの治療のために先進医療を受けたときに、先進医療技術料と同額の給付金が支給される。(特約付加されている場合)など
病気はがんに限定されますが、一般の医療保険と比較して手厚い保障が特徴です。

編集部
8. 女性保険
女性保険も医療保険の一種であり、一般的な病気やけがの保障に加えて、女性特有の病気に対する保障が手厚いことが特徴です。
女性保険の特徴
- 異常分娩への手厚い保障(入院給付金や一時金が上乗せされるなど)
- 乳がん、子宮がんなど女性特有のがんに対する保障が手厚い。
また、上記以外にも「特定の不妊治療」や「正常分娩」に対する保障(入院給付金または出産一時金)が付加された女性保険もあります。
保障内容は保険会社によって異なりますが、女性向けの保障が追加されているため、一般の医療保険と比べると保険料が高くなりがちです。
保障内容による分類
ここまで、医療保険を大きく8種類に分けて解説しましたが、保障内容によっても医療保険は異なる特徴を持ちます。
医療保険の主な保障は、入院給付金と手術給付金で、これらは次のような基準で分類できます。
補償内容による分類
- 入院給付金の1入院あたりの支給限度日数:60日型、120日型、180日型 など
- 入院給付金の通算支給限度日数:700日型、1,000日型、1095日型 など
- 手術給付金の支給金額:所定倍率型(入院給付日額の10倍・20倍・40倍)、一定金額型(入院中の手術:10万円、通院での手術:5万円) など

編集部
民間の医療保険の加入率
ここからは、民間の医療保険の加入率についてご紹介していきます。
年度ごとの加入率の推移をはじめ、年代・性別ごとの加入率をまとめていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
年度ごとの加入率推移
| 年度 | 加入率(%) |
| 令和4年 | 81.6 |
| 令和元年 | 86.8 |
| 平成28年 | 86.5 |
| 平成25年 | 88.1 |
| 平成22年 | 87.9 |
参照:公益財団法人 生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」(P76)より
生命保険文化センターの調査によると、民間保険に加入している人のうち、医療保険に加入している人の割合は81.6%であることが分かっています。

編集部
年代・性別ごとの加入率
| 年齢 | 男性の加入率(%) | 女性の加入率(%) |
| 20歳代 | 32.8 | 47.6 |
| 30歳代 | 68.4 | 72.4 |
| 40歳代 | 74.9 | 76.2 |
| 50歳代 | 72.1 | 77.2 |
| 60歳代 | 75.4 | 77.2 |
参照:公益財団法人 生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」(P71)より
年代・性別ごとの加入率をみてみると、20代は加入率が半数以下と低く、30代以降から一気に加入率が上がっていることが分かります。また、全体的に男性よりも女性の方が加入率が高いことも伺えます。
医療保険に関するよくある質問
公的医療保険があれば、必ずしも民間の医療保険が必要とは限りません。しかし、公的医療保険だけではカバーしきれない費用もあるため、状況に応じて民間の医療保険を検討するのが良いでしょう。
公的医療保険には高額療養費制度があり、自己負担額には上限がありますが、差額ベッド代や先進医療の費用、入院時の生活費などは対象外です。これらの費用が発生した際に、自己負担が大きくなる可能性があります。
公的医療保険でカバーできる範囲と、自身の経済状況によって判断できます。 貯蓄が十分にあり、公的医療費の対象外の費用にも対応できる場合は、民間の医療保険の必要性は低いかもしれません。しかし、貯蓄だけでは不安がある場合や、特定の病気や治療に備えたい場合は、加入を検討するとよいでしょう。
医療保険の分類方法はさまざまですが、保障期間や貯蓄性の有無、特徴のある保障内容などで次の8種類に分けられます。
医療保険の種類一覧
- 定期医療保険
- 終身医療保険
- 掛け捨て型医療保険
- 貯蓄型医療保険
- 引受基準緩和型医療保険
- 無選択医療保険
- がん保険
- 女性保険
詳しくはこちらをご覧ください。
公的医療保険の場合は、病院や診療所などの医療機関で医療行為を受けた際に、医療費の一部を国や健康保険組合などが負担してくれる仕組みです。民間の医療保険の場合は、大勢の加入者で保険料を公平に負担し、治療や入院の際には保険会社より給付金を受け取る仕組みとなっています。
生命保険とは人の生死やけが、病気など人体に関わるリスクに備える保険のことです。つまり、医療保険は数多くある生命保険の一種であると言えます。「死亡保障はいらない」「入院保障を上乗せしたい」など、個別に準備したいというニーズには医療保険がおすすめです。
民間の医療保険は加入する年齢が低いほど、保険料が低い傾向にあります。医療保険が必要だと感じている方は、なるべく早い段階で加入して毎月の負担を抑えつつ、医療費の負担を軽減することをおすすめします。
まとめ
今回は、医療保険とは何か、どんな種類があるのかなど、基本的な情報を簡単にわかりやすく解説しました。日本では、公的医療保険(国民皆保険)と生命保険会社が提供する民間の医療保険があり、どちらも大切な役割を担っています。
日本の皆保険制度により、国民は公的医療保険で医療費の一部をカバーされていますが、全ての医療費を補えるわけではありません。そこで、生命保険会社が提供する医療保険が、カバーしきれないリスクや不足部分を補う役割を果たします。
医療保険にはさまざまな種類があり選択に迷いますが、まずは公的医療保険でカバーできないリスクや、自分に必要な保障内容を理解することが、最適な保険選びへの第一歩です。

編集部
大学卒業後、信用金庫に入社。中立的な立場でお客様目線の営業をしたいという思いから、保険代理店として独立を決意。
保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店『コミヤ保険サービス』を設立。
保険代理店の実務経験を生かして、執筆業や講師業も行う。

人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

岩手県出身。大学卒業後、銀行、外資系生命保険会社、建設業(企業再生)を経て、ほけんのぜんぶに入社。
保険業界経験歴は18年。岩手県生命保険協会副会長も務める。