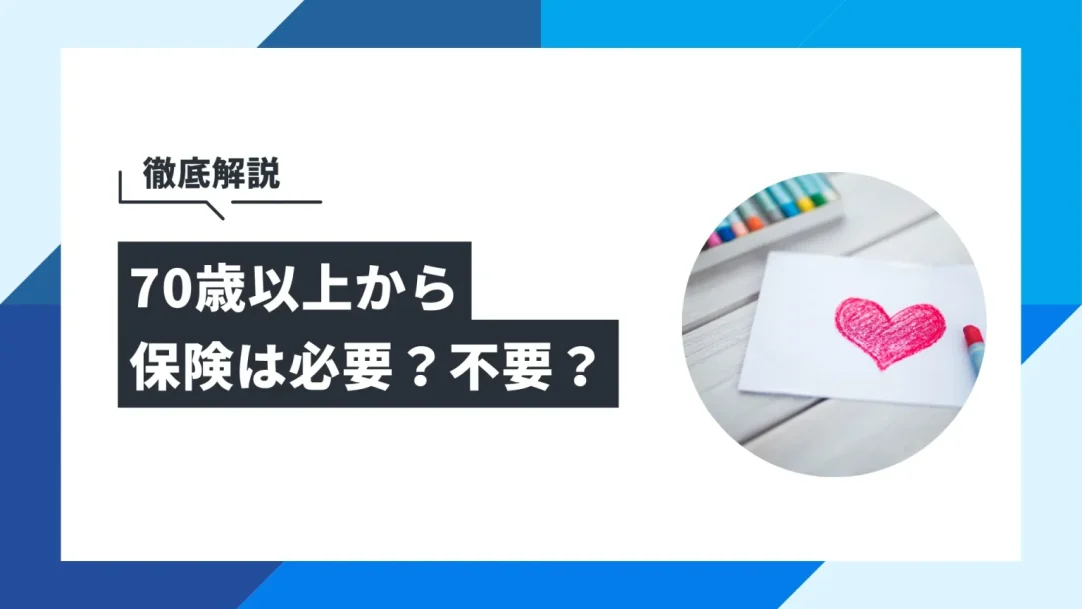銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

70歳を過ぎても保険は必要なのでしょうか?
日本は公的医療保険制度が充実しているので、金銭的負担は少なくなると考えてあまり心配していていない方もおられるかもしれません。
70歳以上の人に保険が必要かどうかは、人によって大きく意見の分かれるところです。この記事では、70歳以上の人にとって本当に保険は必要かについて徹底解説します。

この記事の要点
この記事は5分程度で読めます。
※本コンテンツで紹介している保険会社は、保険業法により金融庁の審査を受け内閣総理大臣から免許を取得しています。コンテンツ内で紹介する商品の一部または全部に広告が含まれています。しかし、当サイトは生命保険協会等の公的機関や保険会社の公式サイトの情報をもとに各商品を公正・公平に比較しているため、情報や評価に影響する事は一切ありません。当コンテンツはほけんのぜんぶが管理しています。詳しくは、広告ポリシーと制作・編集ガイドラインをご覧ください。
【当サイトは金融庁の広告に関するガイドラインに則って運営しています】
金融商品取引法
募集文書等の表示に係るガイドライン
生命保険商品に関する適正表示ガイドライン
広告等に関するガイドライン
目次
70歳以上に保険は必要なのか
70歳を過ぎると、公的医療保険で治療費の自己負担が軽減されますが、それでも医療保険の重要性は変わりません。
また、厚生労働省のデータによると、70歳以上になると入院率は急増します。
| 年齢 | 総数 |
|---|---|
| 60~64歳 | 838 |
| 65~69歳 | 1,117 |
| 70~74歳 | 1,502 |
| 75~79歳 | 2,033 |
出典:厚生労働省「令和5年(2023)患者調査の概況」-2 受療率
公的医療保険で自己負担額が軽減されても、長期の入院や治療には依然として多額の費用がかかります。

編集部
※1 出典:公益財団法人 生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査」P5
70歳以上で持病がある人も入れる可能性が高い保険
保険に加入するには、保険会社が定めた健康状態であることが必要です。持病があれば、診査で加入できないこともあります。
しかし、70歳以上で持病があったり過去に大きな病気をしたりしていても加入できる保険も販売されています。主な種類は次の2つです。
70歳を過ぎても加入できる可能性がある保険
- 引受基準緩和型(限定告知型)
- 無選択型(無告知型)
引受基準緩和型保険(限定告知型)
告知内容も2~4項目くらいに限定されているので、限定告知型保険ともよばれます。主な特徴は次の通りです。
ポイント
- 加入時の持病が悪化した場合も保障の対象となる(病気によっては保障されないケースもある)
- 保険料は一般の保険よりも割高な傾向にある
- 免責期間(加入後一定期間は半額支給など)がある
(保険会社によっては、給付金の削減期間のない緩和型医療保険を取り扱っている会社もあります。)
無選択型保険(無告知型)
告知が全く不要なので無告知型保険ともよばれます。主な特徴は次の通りです。
ポイント
- 加入時の持病が悪化した場合は基本的に保障されない
- 保険料は一般の保険よりも割高な傾向にある(引受基準緩和型保険よりも割高)
- 保障は一般の保険よりも少ないことが多い
引受基準緩和型保険や無選択型保険は、持病があっても加入できる一方、保険料が割高な傾向にある保険です。
70歳以上は保険の見直しが必須
70歳以上になると、医療費の負担軽減措置がある一方で、病気や入院のリスクが高まります。そのため、医療保険の見直しが必要です。
まず、現在加入している医療保険の保障内容と保険料を確認し、以下のポイントをチェックしましょう。
保障内容の見直しポイント
保障内容でチェックすべきポイント
- 入院給付日額
- 給付金が支給される要件
- 医療保険の保障期間
まず最初に確認したいのは「入院給付日額」です。高額療養費制度で治療費の負担が軽減されても、差額ベッド代や病院での生活費は自己負担となります。入院が長引けば負担が大きくなるため、保険でどこまでカバーできるか確認しましょう。
次に確認したいのは「給付金が支給される要件」です。特に、「免責期間」、「高額治療の支給可否」、「無制限支給の有無」などを確認しておきましょう。自由診療や先進医療は保険適用外のため、自己負担が高額になる可能性があります。
最後は「保障期間」です。保障内容が優れていても、保険が満期を迎えてしまっては意味がありません。終身タイプの医療保険なら問題ありませんが、定期タイプの場合は保障期間が満了する前に見直しを検討しましょう。
保険料の確認
70歳以上の医療保険では、保険料の水準と更新の有無の確認も必要です。
老後は収入が限られている場合が多いため、保険料が家計に与える負担を把握し、必要に応じて保険料を抑える方法を検討しましょう。
特に更新タイプの保険では、更新後の保険料が上がる可能性があるため、その支払いが可能かどうかをチェックすることが大切です。
70歳以上の人が公的医療保険制度で軽減される金額
70歳になると病院で治療を受けたとき窓口負担が下がったり、高額療養費制度の自己負担限度額が軽減したりします。また、75歳になると後期高齢者医療制度に加入することになり、再度、治療費の窓口負担などが変わります。
70歳以降の公的医療保険制度の負担額についてみていきましょう。
医療費の負担額とは
病院で治療を受けたとき窓口で負担するのは、原則治療費の3割です。しかし、70歳になると治療費の負担割合は原則2割、75歳になると原則1割に軽減されます。
注意点
ただし、現役並みの収入がある人は、70歳になっても75歳になっても治療費の負担割合は3割のままです。
70歳以上75歳未満の人の医療費
70歳以上75歳未満の人の医療費の負担割合は、収入と誕生日によって次の通りに決まります。
| 収入(誕生日) | 医療費の負担割合 | |
| (健保)標準報酬月額28万円未満
(国保)課税所得145万円未満 |
(昭和19年4月2日以降) | 2割 |
|---|---|---|
| (昭和19年4月1日以前) | 1割 | |
|
(健保)標準報酬月額28万円以上 (国保)課税所得145万円以上 |
3割 | |
※標準報酬月額:被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの。
参考:全国健康保険協会「高齢受給者証」
誕生日が昭和19年4月2日以降の人は、平成26年4月1日以降に70歳になる人です。

編集部
しかし、既に70歳になっていた昭和19年4月1日以前生まれの人は、「一部負担金等の軽減特例措置」により負担割合が1割に据え置かれました。
ポイント
負担割合が3種類もあって分かりにくそうですが、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の場合は前月)に交付される「高齢受給者証」に負担割合が記載されています。
75歳以上の人の医療費
後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の人の医療費の負担割合は、収入によって次の通りに決まります。
| 課税所得 | 医療費の負担割合 |
|---|---|
| 145万円未満 | 1割 |
| 145万円以上 | 3割 |
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
高齢になるほど病院に通う頻度は高くなるので、現役並みの収入がある人を除けば医療費の負担割合の軽減はありがたい制度ですね。

編集部
公的医療保険制度で軽減される項目や金額とは
病院での窓口負担のほか、公的医療保険制度で軽減されるのは「高額療養費制度」や「高額介護合算療養費」の自己負担限度額などです。
高額療養費制度
※認定書などの提示により窓口で超過分を支払わない方法もあります。

編集部
年収などに応じて、次の通り「世帯全体の治療費」と「外来に限定した個人の治療費」の自己負担限度額が決められています。
表は横にスライドできます
| 区分(年収) | 外来の自己負担限度額(個人) | 自己負担限度額(世帯) |
| 約1,160万円~
標準報酬83万円以上/課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000)×1% | |
|---|---|---|
| 約770万円~約1,160万円
標準報酬53万円~79万円/課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
| 約370万円~約770万円
標準報酬28万円~50万円/課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
| 一般
標準報酬26万円以下/課税所得145万円未満等 |
18,000円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) | 8,000円 | 15,000円 |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
70歳になって自己負担限度額が軽減されるのは、区分が「一般」と「住民税非課税世帯」の人です。
注意点
年収約370万円以上の人は、「現役並み」として取り扱われ70歳未満の人と同額の負担をしなければなりません。
高額介護合算療養費
高額療養費制度とは異なり、1年通算した自己負担額に対して限度額が設けられています。自己負担限度額は次の通りです。
| 区分(年収) | 自己負担限度額(世帯) |
| 約1,160万円~
標準報酬83万円以上/課税所得690万円以上 |
212万円 |
|---|---|
| 約770万円~約1,160万円
標準報酬53万円~79万円/課税所得380万円以上 |
141万円 |
| 約370万円~約770万円
標準報酬28万円~50万円/課税所得145万円以上 |
67万円 |
| 一般
標準報酬26万円以下/課税所得145万円未満等 |
56万円 |
| 住民税非課税世帯 | 31万円 |
| 住民税非課税世帯 (所得が一定以下) | 19万円※ |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」

編集部
70歳以上で保険が必要な人・不要な人
70歳以上で保険が必要かどうかは、主に老後の収入や資産状況に基づいて判断されます。以下のポイントを考慮しましょう。
70歳以上で医療保険が必要な人
医療保険が必要な人
- 収入や資産が不足している場合
- 年金収入が少なく、仕事をしている場合
- 先進医療を希望する場合
公的医療保険制度は、治療費の軽減や自己負担額の上限をカバーしますが、差額ベッド代や先進医療、入院中の生活費などは対象外です。これらの費用を賄える収入や資産がない場合は、医療保険の必要性が高いでしょう。
また、年金収入が少ない場合、日常生活費や治療費を十分に賄うためには手厚い保障が求められます。特に、治療が長期化した場合や差額ベッド代を支払う余裕がない場合には、一定額の入院保障が必要です。
先進医療など充実した治療への費用を保険で準備したい場合は、必要な特約を付加した医療保険への加入を検討すると良いでしょう。
70歳以上で医療保険が不要な人
医療保険が不要な人
- 高収入で安定した収入源がある場合
- 十分な資産がある場合
70歳以上で不動産収入や十分な資産があり、治療費や生活費を自分で賄える場合、医療保険の必要性は低いといえます。
自身の資産で生活費や治療費を賄える状況では、医療保険に加入する必要があまりないからです。

編集部
終身保険は、万が一の際に残された家族に確実に資産を残し、相続税対策にもなります。
まとめ
保険は働き盛りの責任世代のためだけのものではありません。
70歳以上になると、公的医療保険制度により治療費負担などは軽減しますが、病気のリスクは高くなるので保険適用外の費用に対する備えが必要です。
平均寿命が延びて老後生活が長期化する中、貴重な老後資金が大きく減らないように70歳以上の方も保険を上手に活用しましょう。
これまで掛けてきた保険をベースにして、無駄を省き不足分を補いましょう。
人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。