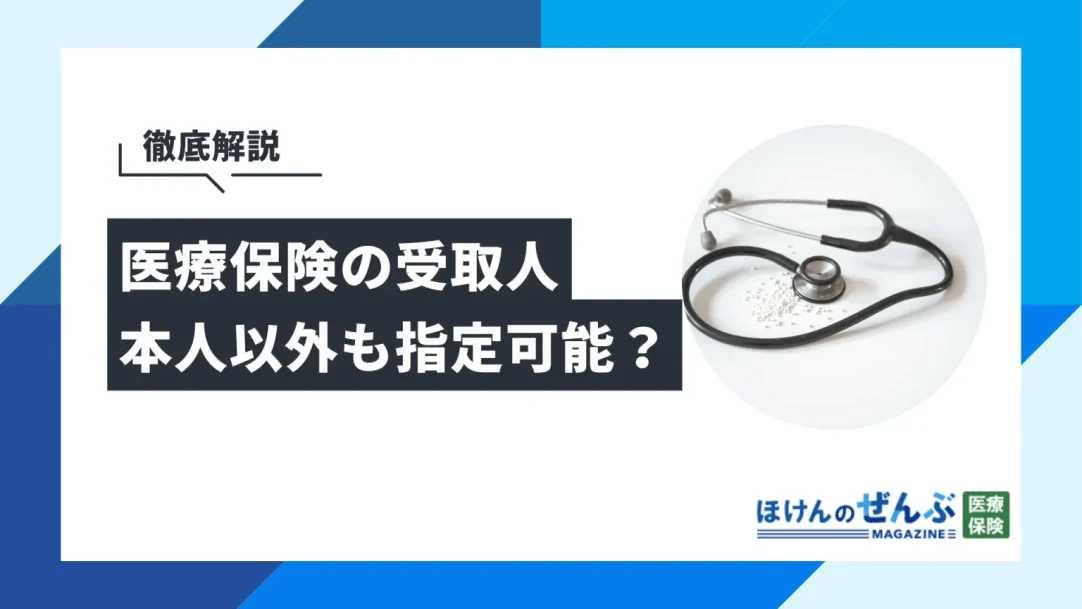銀行出身のFP(ファイナンシャルプランナー)。現在は、ほけんのぜんぶに所属。 20~80代の方まで幅広い相談に対応。お金の事だけでなく、自身の子育て経験を踏まえた提案に定評。

医療保険を契約するときは「契約者」と「被保険者」のほかに、誰が保険金を受け取る権利を持つか「受取人」を設定する必要があります。
現代の医療保険では、通常、被保険者=受取人となっていることが多いですが、ケガや病気の状態によっては、被保険者自身が給付金を申請できない場合もあります。
その場合、受取人以外の人物が給付金を申請することは可能なのでしょうか?

この記事の要点
この記事は5分程度で読めます。
医療保険の受取人とは
医療保険の契約においては、以下の3者が関わり合うことになります。
医療保険契約の3者の役割
- 契約者:保険会社と契約を結ぶ人
- 被保険者:保険の対象となる人
- 受取人:給付金や保険金を受け取る人
医療保険において、入院や通院などの給付金は被保険者本人が受け取ります。死亡保険金については、配偶者や子どもが受取人となることが一般的です。
契約の仕方によって税金の種類や金額が異なるため、給付金の受け取り方については税金の影響も考慮に入れて決めていくことが大切です。
受取人の確認方法
保険契約が長期間続くと、受取人が誰だったかを忘れてしまいそうですよね。しかし、通常受取人の情報は保険証券や毎年送られてくる「現在のご契約内容のお知らせ」に記載されています。
外出先で受取人を確認したい場合は、ネットで契約した医療保険であれば、公式ウェブサイトの会員ページにログインすることで確認が可能です。
保険会社によって確認方法は変わりますが、基本的には以下の流れで確認できます。
受取人の確認方法(公式webサイト例)
- 利用者の会員ページにログイン
- 「契約内容の照会」をクリック
- 契約内容の「受取人」欄を確認する
ケガや病気になった際に手続きで困らないよう、受取人の確認方法も日頃から理解しておくようにしましょう。
医療保険の受取人は本人以外でも指定可能?
医療保険には受取人の設定が必要ですが、誰でも受取人になれるのでしょうか?例えば、血縁関係がないパートナーや友人を受取人に指定できるのか気になる方もいるでしょう。
ここでは、医療保険の受取人に関するルールを詳しく解説します。
医療保険の給付金受取人は基本的に「被保険者」
現行の医療保険では、入院給付金・手術給付金の受取人はほとんどの場合「被保険者」となります。
医療保険の被保険者として契約できるのは、以下のような人です。
医療保険の被保険者になれる人
- 契約者本人
- 配偶者
- 2親等以内の血族(父、母、子ども、兄弟姉妹、祖父母、孫など)
「2親等以内の血族」とは、父・母・子ども・兄弟姉妹・祖父母・孫といった近しい血縁関係にある人を指します。

編集部
契約者以外の人を被保険者にする際の注意点
契約者以外を被保険者にすると、受取人と被保険者が同一でなくても給付金を請求できるなどのメリットがあります。
特に、被保険者が治療を受けている最中に、自分で請求手続きができない状況になると、保険金の請求が遅れるリスクがあります。

編集部
受取人以外でも給付金を請求できるケースとは?
医療保険の給付金は通常、受取人のみが請求できます。
しかし、受取人が病気やケガで請求できない場合、「指定代理請求人」を設定することで、受取人以外でも給付金を請求することが可能です。
指定代理請求人が必要となるシチュエーションとしては、以下のような場合があります。
- 被保険者のケガや病気の状態が重く、請求する意思を示せない場合
- 被保険者ががんなどの病気によって、病名や余命を告知されていない場合

編集部
医療保険の保険金受け取りにまつわる税金について
保険を利用して保険金や給付金(一時金)を受け取る場合、意外と見落としがちになるのが税金の関係です。

編集部
ここでは、医療保険と税金の関係について解説します。
医療保険の給付金は非課税
医療保険の給付金に関して、被保険者本人や配偶者、直系血族のほか、被保険者と生計をともにする親族であれば受け取っても税金を支払う必要はありません。
非課税になる対象は、以下のような給付です。
非課税対象になる給付
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- 三大疾病給付金
- がん診断給付金(がん保険の場合)
これは「所得税法施行令第30条」において、身体の傷害や疾病に基因して支払われる特定の給付金が非課税と定められているためです。
出典:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)|e-Gov 法令検索
給付金が課税されるケースとは
医療保険の給付金が課税されるのは、受取人以外の人が受け取った場合です。例えば、「親が亡くなり、遺品整理中に医療保険の証書を見つけた」といったケースが該当します。
病気で亡くなった場合でも、亡くなるまでに入院していれば、その入院期間に応じた入院給付金を受け取れます。手術や通院があった場合も同様に、給付金を受け取ることが可能です。
通常、医療保険の給付金は本人が請求しますが、亡くなっている場合は遺族が請求することになります。
もし遺言が残されていない場合、遺族は相続時に遺産分割協議を行い、財産を分配することになります。

死亡保険金は受取人によって税金が変わる
医療保険の死亡保険金で課税される区分、金額は「契約者」「被保険者」「死亡保険金受取人」の組み合わせによって異なります。
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税区分 | |
| 契約者=被保険者 | 夫 | 夫 | 妻や子 | 相続税 |
|---|---|---|---|---|
| 契約者=受取人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
| 全て異なる | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
契約者と被保険者が同じ場合
契約者、被保険者、受取人がA・A・Bの関係、つまり契約者と被保険者が同じ人物で受取人が別の人の場合、死亡保険金は相続財産扱いになります。
相続として受け取る人が法定相続人の場合は「非課税枠」によって相続税負担が安く抑えられるようになっており、非課税枠の計算式は以下のとおりです。
死亡保険金の受取人が配偶者と子どもの2人の場合、1,000万円までの死亡保険金が非課税になります。

編集部
契約者と受取人が同じ場合
契約者、被保険者、受取人がA・B・Aの関係、つまり契約者と受取人が同じ場合は「一時所得」として所得税・住民税の課税対象になります。
このことから、受け取った死亡保険金とこれまでに支払った保険料の差が50万円以下である場合は非課税で、税金を支払う必要はありません。

編集部
契約者、被保険者、受取人の全てが異なる場合
契約者、被保険者、受取人のA・B・Cの関係で3者全員が異なるケースでは、Cが受け取る死亡保険金は贈与の扱いになります。
贈与では年間110万円の基礎控除がありますが、それを超えた分に課税されます。
この贈与税の区分では一時所得とは違って支払った保険料の金額がマイナスされることがないため、税負担は相続税や所得税と比較して最も重くなる可能性が高いのが特徴です。
出典:No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
医療保険の受取人は途中で変更できる?
医療保険の受取人は、契約内容や給付金の種類によって変更できる場合があります。
受取人変更には条件があり、特に「被保険者」と指定されている場合や、受取人を選べるタイプかどうかで対応が異なります。
受取人が死亡した場合は法定相続人が受取人になる
被保険者より先に生命保険の受取人が死亡した場合、保険会社に連絡して受取人の変更手続きが必要です。

受取人変更の手続きをしていなかった場合は被保険者の法定相続人ではなく、受取人の法定相続人が受取人の地位を引き継ぐことになります。
夫が契約者と被保険者、妻が受取人の場合、妻が夫より先に亡くなったときは子どもが受取人になります。
子どもがいない場合は妻の両親、両親もすでに亡くなっているときは妻の兄弟姉妹が受け取ることになるのが原則の順番です。
保険金・給付金の種類によって変更可能かが異なる
給付金受取人の変更
給付金受取人は、契約内容に基づき変更可能な場合があります。
ただし、契約内容によっては変更が制限されていることもあり、特に被保険者と同一人物でなければならない受取人の場合は、変更できないことがあります。

編集部
死亡保険金受取人の変更
死亡保険金受取人の場合、被保険者の同意があればいつでも変更できます。
医療保険の死亡保険金は少額であることが多く、税負担が軽い場合が多いものの、贈与税や相続税が発生する場合もあるため、受取人変更時には税制面を考慮することが大切です。
まとめ
現在の医療保険では、ほとんどの場合で被保険者=受取人です。そのため、ケガや病気で重症のために給付金の申請ができないことが考えられます。
そうならないためにも、医療保険に加入する際は受取人と一緒に「指定代理請求人」の設定を検討しましょう。
また、受取人が給付金を受け取る前に亡くなった場合は相続の対象になるため、税金の問題が発生します。
税金の問題は複雑ですが、受け取る人によっては多額の相続税、所得税、贈与税などの支払いが必要になるため注意が必要です。
受取後の税金まで考えたうえで、受取人を決めておきましょう。
大学卒業後、信用金庫に入社。中立的な立場でお客様目線の営業をしたいという思いから、保険代理店として独立を決意。
保険会社の代理店営業職、保険会社の研修生を経て2020年9月に保険代理店『コミヤ保険サービス』を設立。
保険代理店の実務経験を生かして、執筆業や講師業も行う。

人材派遣会社17年経営したのち、保険代理店に転身後16年従事、2級FP技能士・トータルライフコンサルタント・MDRT成績資格会員2度取得。
ファイナンシャルプランナーとしてライフプランニングや家計診断を通して老後資金の対策、節約術などを提案。
また自らのがん闘病経験をふまえた生きる応援・備えるべき保障の大切さをお伝えしています。

岩手県出身。大学卒業後、銀行、外資系生命保険会社、建設業(企業再生)を経て、ほけんのぜんぶに入社。
保険業界経験歴は18年。岩手県生命保険協会副会長も務める。